貞女は二夫に見えずとは
貞女は二夫に見えず
ていじょはじふにまみえず
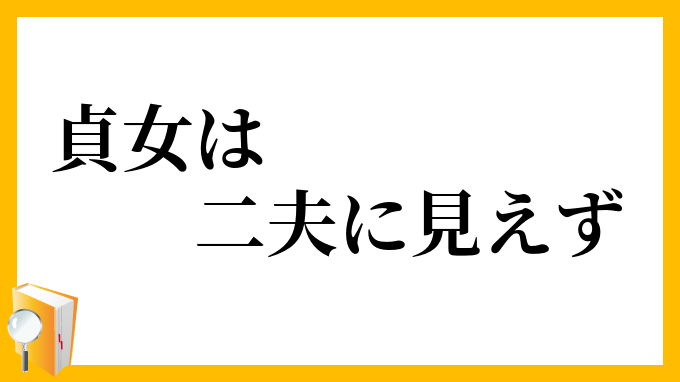
| 言葉 | 貞女は二夫に見えず |
|---|---|
| 読み方 | ていじょはじふにまみえず |
| 意味 | 貞淑な女性は夫が亡くなっても、再び他の夫をもつことはしないということ。
「じふ」は「にふ」ともいう。 また、「貞女は両夫に見えず」「貞女は二夫を更めず」「貞女は二夫を並べず」などともいう。 |
| 異形 | 貞女は両夫に見えず(ていじょはりょうふにまみえず) |
| 貞女は二夫を更めず(ていじょはじふをあらためず) | |
| 貞女は二夫を並べず(ていじょはじふをならべず) | |
| 場面用途 | 夫婦 / 親族 |
| 使用漢字 | 貞 / 女 / 二 / 夫 / 見 / 両 / 更 / 並 |
「貞」を含むことわざ
- 貞女は二夫に見えず(ていじょはじふにまみえず)
- 貞女は二夫を更めず(ていじょはじふをあらためず)
- 貞女は二夫を並べず(ていじょはじふをならべず)
- 貞女は両夫に見えず(ていじょはりょうふにまみえず)
「女」を含むことわざ
- 悪女の深情け(あくじょのふかなさけ)
- 悪女は鏡を疎む(あくじょはかがみをうとむ)
- 朝雨と女の腕捲り(あさあめとおんなのうでまくり)
- 東男に京女(あずまおとこにきょうおんな)
- 姉女房は身代の薬(あねにょうぼうはしんだいのくすり)
- 家に女房なきは火のない炉のごとし(いえににょうぼうなきはひのないろのごとし)
- 厭じゃ厭じゃは女の癖(いやじゃいやじゃはおんなのくせ)
- 入り鉄砲に出女(いりでっぽうにでおんな)
- 男の目には糸を引け、女の目には鈴を張れ(おとこのめにはいとをひけ、おんなのめにはすずをはれ)
- 男は度胸、女は愛嬌(おとこはどきょう、おんなはあいきょう)
「二」を含むことわざ
- 青二才(あおにさい)
- 朝の一時は晩の二時に当たる(あさのひとときはばんのふたときにあたる)
- 値を二つにせず(あたいをふたつにせず)
- 一瓜実に二丸顔(いちうりざねににまるがお)
- 一応も二応も(いちおうもにおうも)
- 一押し、二金、三男(いちおし、にかね、さんおとこ)
- 一髪、二化粧、三衣装(いちかみ、にけしょう、さんいしょう)
- 一工面、二働き(いちくめん、にはたらき)
- 一度あることは二度ある(いちどあることはにどある)
- 一度死ねば二度死なぬ(いちどしねばにどしなぬ)
「夫」を含むことわざ
- 秋風と夫婦喧嘩は日が入りゃ止む(あきかぜとふうふげんかはひがいりゃやむ)
- 一夫関に当たれば万夫も開くなし(いっぷかんにあたればばんぷもひらくなし)
- 同い年夫婦は火吹く力もない(おないどしみょうとはひふくちからもない)
- 親子は一世、夫婦は二世、主従は三世(おやこはいっせ、ふうふはにせ、しゅじゅうはさんせ)
- 漁夫の利(ぎょふのり)
- 三軍も帥を奪うべきなり、匹夫も志を奪うべからず(さんぐんもすいをうばうべきなり、ひっぷもこころざしをうばうべからず)
- 大丈夫、金の脇差(だいじょうぶ、かねのわきざし)
「見」を含むことわざ
- 相手見てからの喧嘩声(あいてみてからのけんかごえ)
- 青菜は男に見せな(あおなはおとこにみせな)
- 青菜は男に見せるな(あおなはおとこにみせるな)
- 足下を見る(あしもとをみる)
- 足元を見る(あしもとをみる)
- 後先見ず(あとさきみず)
- 穴の開くほど見る(あなのあくほどみる)
- 甘く見る(あまくみる)
- いい目を見る(いいめをみる)
- 戦を見て矢を矧ぐ(いくさをみてやをはぐ)
「両」を含むことわざ
- 朝起き三両始末五両(あさおきさんりょうしまつごりょう)
- 朝起き千両(あさおきせんりょう)
- 朝起き千両、夜起き百両(あさおきせんりょう、よおきひゃくりょう)
- 後ろ千両前一文(うしろせんりょうまえいちもん)
- 堪忍五両、思案十両(かんにんごりょう、しあんじゅうりょう)
- 堪忍五両、負けて三両(かんにんごりょう、まけてさんりょう)
- がったり三両(がったりさんりょう)
- 車の両輪(くるまのりょうりん)
- 喧嘩両成敗(けんかりょうせいばい)
- 御意見五両、堪忍十両(ごいけんごりょう、かんにんじゅうりょう)
「更」を含むことわざ
- 貞女は二夫を更めず(ていじょはじふをあらためず)
- 満更でもない(まんざらでもない)



