戦を見て矢を矧ぐとは
戦を見て矢を矧ぐ
いくさをみてやをはぐ
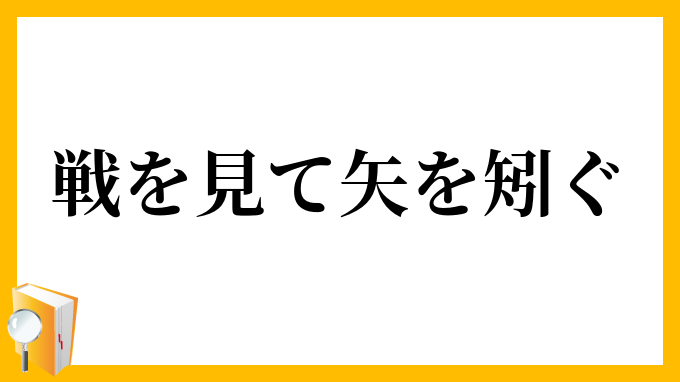
| 言葉 | 戦を見て矢を矧ぐ |
|---|---|
| 読み方 | いくさをみてやをはぐ |
| 意味 | 物事が起こってから、慌てて準備にとりかかる愚かさをいう言葉。
戦いが始まってから矢を作ることから。 「軍を見て矢を矧ぐ」「敵を見て矢を矧ぐ」ともいう。 |
| 異形 | 軍を見て矢を矧ぐ(いくさをみてやをはぐ) |
| 敵を見て矢を矧ぐ(てきをみてやをはぐ) | |
| 類句 | 泥棒を捕らえて縄を綯う(どろぼうをとらえてなわをなう) |
| 盗人を捕らえて縄を綯う(ぬすびとをとらえてなわをなう) | |
| 渇に臨みて井を穿つ(かつにのぞみていをうがつ) | |
| 使用語彙 | 矧ぐ |
| 使用漢字 | 戦 / 見 / 矢 / 矧 / 軍 / 敵 |
「戦」を含むことわざ
- 一戦に及ぶ(いっせんにおよぶ)
- 一戦を交える(いっせんをまじえる)
- 彼を知り己を知れば百戦殆うからず(かれをしりおのれをしればひゃくせんあやうからず)
- 冷たい戦争(つめたいせんそう)
- 天下分け目の戦い(てんかわけめのたたかい)
- 腹が減っては戦ができぬ(はらがへってはいくさができぬ)
- 百戦百勝は善の善なる者に非ず(ひゃくせんひゃくしょうはぜんのぜんなるものにあらず)
- 法師の戦話(ほうしのいくさばなし)
「見」を含むことわざ
- 相手見てからの喧嘩声(あいてみてからのけんかごえ)
- 青菜は男に見せな(あおなはおとこにみせな)
- 青菜は男に見せるな(あおなはおとこにみせるな)
- 足下を見る(あしもとをみる)
- 足元を見る(あしもとをみる)
- 後先見ず(あとさきみず)
- 穴の開くほど見る(あなのあくほどみる)
- 甘く見る(あまくみる)
- いい目を見る(いいめをみる)
「矢」を含むことわざ
- 石に立つ矢(いしにたつや)
- 一矢を報いる(いっしをむくいる)
- 刀折れ矢尽きる(かたなおれやつきる)
- 帰心、矢の如し(きしん、やのごとし)
- 狐が下手の射る矢を恐る(きつねがへたのいるやをおそる)
- 光陰、矢の如し(こういん、やのごとし)
- 白羽の矢が立つ(しらはのやがたつ)
「矧」を含むことわざ
- 戦を見て矢を矧ぐ(いくさをみてやをはぐ)
- 軍を見て矢を矧ぐ(いくさをみてやをはぐ)
- 敵を見て矢を矧ぐ(てきをみてやをはぐ)
「軍」を含むことわざ
- 勝てば官軍(かてばかんぐん)
- 勝てば官軍、負ければ賊軍(かてばかんぐん、まければぞくぐん)
- 軍門に降る(ぐんもんにくだる)
- 軍門に下る(ぐんもんにくだる)
- 三軍も帥を奪うべきなり、匹夫も志を奪うべからず(さんぐんもすいをうばうべきなり、ひっぷもこころざしをうばうべからず)
- 大軍に関所なし(たいぐんにせきしょなし)
- 敗軍の将は兵を語らず(はいぐんのしょうはへいをかたらず)



