敗軍の将は兵を語らずとは
敗軍の将は兵を語らず
はいぐんのしょうはへいをかたらず
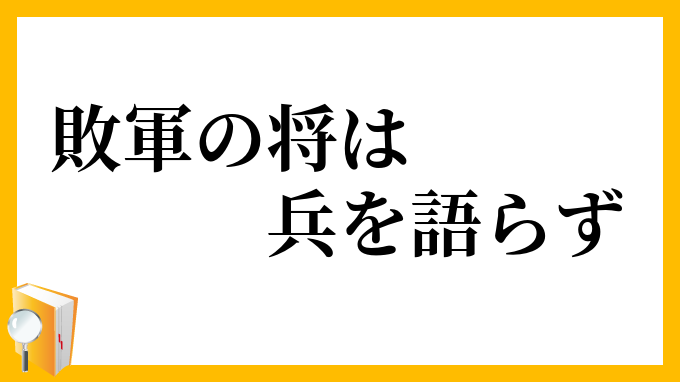
| 言葉 | 敗軍の将は兵を語らず |
|---|---|
| 読み方 | はいぐんのしょうはへいをかたらず |
| 意味 | 失敗した者は、そのことについて弁解する資格がないということ。戦いに敗れた将軍は兵法について発言する資格はないとの意から。 |
| 出典 | 『史記』 |
| 使用語彙 | 敗軍 / 敗 / 兵 |
| 使用漢字 | 敗 / 軍 / 将 / 兵 / 語 |
「敗」を含むことわざ
- 一敗、地に塗れる(いっぱい、ちにまみれる)
- 喧嘩両成敗(けんかりょうせいばい)
- 失敗は成功のもと(しっぱいはせいこうのもと)
- 敗軍の将は兵を語らず(はいぐんのしょうはへいをかたらず)
「軍」を含むことわざ
- 軍を見て矢を矧ぐ(いくさをみてやをはぐ)
- 勝てば官軍、負ければ賊軍(かてばかんぐん、まければぞくぐん)
- 軍門に降る(ぐんもんにくだる)
- 軍門に下る(ぐんもんにくだる)
- 三軍も帥を奪うべきなり、匹夫も志を奪うべからず(さんぐんもすいをうばうべきなり、ひっぷもこころざしをうばうべからず)
- 大軍に関所なし(たいぐんにせきしょなし)
「将」を含むことわざ
- 一将功成りて万骨枯る(いっしょうこうなりてばんこつかる)
- 王侯将相寧んぞ種あらんや(おうこうしょうしょういずくんぞしゅあらんや)
- お山の大将(おやまのたいしょう)
- 碁で負けたら将棋で勝て(ごでまけたらしょうぎでかて)
- 将棋倒し(しょうぎだおし)
- 将を射んと欲すれば先ず馬を射よ(しょうをいんとほっすればまずうまをいよ)
- 手のない将棋は負け将棋(てのないしょうぎはまけしょうぎ)
- 鳥の将に死なんとする、その鳴くや哀し(とりのまさにしなんとする、そのなくやかなし)
- 万卒は得易く、一将は得難し(ばんそつはえやすく、いっしょうはえがたし)
「兵」を含むことわざ
- 寇に兵を藉し、盗に糧を齎す(あだにへいをかし、とうにかてをもたらす)
- 権兵衛が種蒔きゃ烏がほじくる(ごんべえがたねまきゃからすがほじくる)
- 知らぬ顔の半兵衛(しらぬかおのはんべえ)
- 短兵急(たんぺいきゅう)
- 長崎ばってん、江戸べらぼう、神戸兵庫のなんぞいや、ついでに丹波のいも訛(ながさきばってん、えどべらぼう、こうべひょうごのなんぞいや、ついでにたんばのいもなまり)
- 名無しの権兵衛(ななしのごんべえ)
- 生兵法は大怪我の基(なまびょうほうはおおけがのもと)
- 兵強ければ則ち滅ぶ(へいつよければすなわちほろぶ)
- 兵は詭道(へいはきどう)



