金の貸し借り不和の基とは
金の貸し借り不和の基
かねのかしかりふわのもと
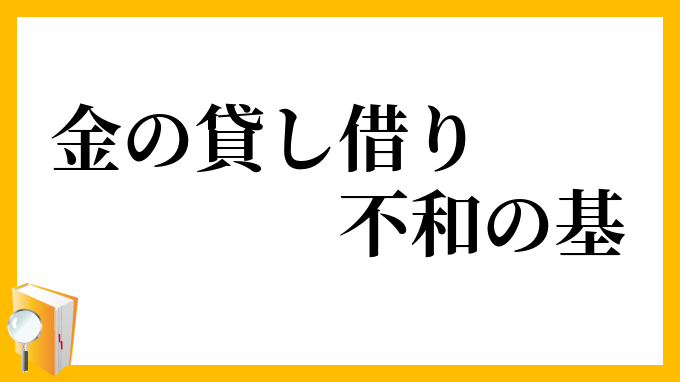
| 言葉 | 金の貸し借り不和の基 |
|---|---|
| 読み方 | かねのかしかりふわのもと |
| 意味 | 金の貸し借りは仲たがいの原因になりがちだから気をつけよという戒め。 |
| 異形 | 金の貸し借りは不和の基(かねのかしかりはふわのもと) |
| 類句 | 金を貸せば友を失う(かねをかせばともをうしなう) |
| 使用語彙 | 貸し借り / 貸し / 不和 |
| 使用漢字 | 金 / 貸 / 借 / 不 / 和 / 基 |
「金」を含むことわざ
- 愛想づかしも金から起きる(あいそづかしもかねからおきる)
- 朝の果物は金(あさのくだものはきん)
- 価千金(あたいせんきん)
- 値千金(あたいせんきん)
- 阿弥陀の光も金次第(あみだのひかりもかねしだい)
- 有り金をはたく(ありがねをはたく)
- ありそうでないのが金(ありそうでないのがかね)
- 石部金吉鉄兜(いしべきんきちかなかぶと)
- 一押し、二金、三男(いちおし、にかね、さんおとこ)
- いつまでもあると思うな親と金(いつまでもあるとおもうなおやとかね)
「貸」を含むことわざ
- 馬持たずに馬貸すな(うまもたずにうまかすな)
- 顔を貸す(かおをかす)
- 傘と提灯は戻らぬつもりで貸せ(かさとちょうちんはもどらぬつもりでかせ)
- 貸し借りは他人(かしかりはたにん)
- 貸した物は忘れぬが借りたものは忘れる(かしたものはわすれぬがかりたものはわすれる)
- 肩を貸す(かたをかす)
- 金を貸したのが円の切れ目(かねをかしたのがえんのきれめ)
- 金を貸せば友を失う(かねをかせばともをうしなう)
「借」を含むことわざ
- 負わず借らずに子三人(おわずからずにこさんにん)
- 蛙の目借り時(かえるのめかりどき)
- 貸し借りは他人(かしかりはたにん)
- 貸した物は忘れぬが借りたものは忘れる(かしたものはわすれぬがかりたものはわすれる)
- 敵の前より借金の前(かたきのまえよりしゃっきんのまえ)
- 借り着より洗い着(かりぎよりあらいぎ)
- 借りて借り得、貸して貸し損(かりてかりどく、かしてかしぞん)
- 借りてきた猫(かりてきたねこ)
「不」を含むことわざ
- 相手にとって不足はない(あいてにとってふそくはない)
- 合うも不思議合わぬも不思議(あうもふしぎあわぬもふしぎ)
- 悪妻は百年の不作(あくさいはひゃくねんのふさく)
- 悪妻は六十年の不作(あくさいはろくじゅうねんのふさく)
- 医者の不養生(いしゃのふようじょう)
- 一抹の不安(いちまつのふあん)
- 一生の不作(いっしょうのふさく)
- 後ろ弁天、前不動(うしろべんてん、まえふどう)
- 置き酌失礼、持たぬが不調法(おきじゃくしつれい、もたぬがぶちょうほう)
「和」を含むことわざ
- 秋日和半作(あきびよりはんさく)
- 和氏の璧(かしのたま)
- 和氏の璧(かしのへき)
- 琴瑟相和す(きんしつあいわす)
- 君子は和して同ぜず、小人は同じて和せず(くんしはわしてどうぜず、しょうじんはどうじてわせず)
- 心安いは不和の基(こころやすいはふわのもと)
- 衣ばかりで和尚はできぬ(ころもばかりでおしょうはできぬ)
- 地の利は人の和に如かず(ちのりはひとのわにしかず)



