蠟燭は身を減らして人を照らすとは
蠟燭は身を減らして人を照らす
ろうそくはみをへらしてひとをてらす
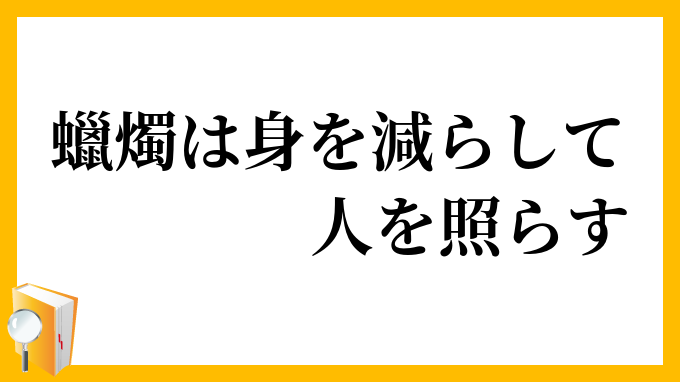
| 言葉 | 蠟燭は身を減らして人を照らす |
|---|---|
| 読み方 | ろうそくはみをへらしてひとをてらす |
| 意味 | 自分の身を犠牲にして、他人のためにつくすことのたとえ。 |
| 場面用途 | 他人 |
| 使用語彙 | 身 / 人 |
| 使用漢字 | 蠟 / 燭 / 身 / 減 / 人 / 照 |
「蠟」を含むことわざ
- 蠟燭は身を減らして人を照らす(ろうそくはみをへらしてひとをてらす)
「燭」を含むことわざ
- 華燭の典(かしょくのてん)
- 蠟燭は身を減らして人を照らす(ろうそくはみをへらしてひとをてらす)
「身」を含むことわざ
- 垢も身のうち(あかもみのうち)
- 悪事、身にかえる(あくじ、みにかえる)
- 悪銭身に付かず(あくせんみにつかず)
- 明日は我が身(あすはわがみ)
- 仇も情けも我が身より出る(あだもなさけもわがみよりでる)
- 姉女房は身代の薬(あねにょうぼうはしんだいのくすり)
- 生き身は死に身(いきみはしにみ)
- 一朝の怒りにその身を忘る(いっちょうのいかりにそのみをわする)
- 憂き身をやつす(うきみをやつす)
- 易者、身の上知らず(えきしゃ、みのうえしらず)
「減」を含むことわざ
- 医者の薬も匙加減(いしゃのくすりもさじかげん)
- 口が減らない(くちがへらない)
- 死なぬものなら子は一人、減らぬものなら金百両(しなぬものならこはひとり、へらぬものならかねひゃくりょう)
- 弟子は師匠の半減(でしはししょうのはんげん)
- 飲むに減らで吸うに減る(のむにへらですうにへる)
- 腹が減っては戦ができぬ(はらがへってはいくさができぬ)
- 減らず口を叩く(へらずぐちをたたく)
- 減らぬものなら金百両、死なぬものなら子は一人(へらぬものならかねひゃくりょう、しなぬものならこはひとり)
- 負け惜しみの減らず口(まけおしみのへらずぐち)
「人」を含むことわざ
- 赤の他人(あかのたにん)
- 商人と屏風は直ぐには立たぬ(あきんどとびょうぶはすぐにはたたぬ)
- 商人と屏風は曲がらねば立たぬ(あきんどとびょうぶはまがらねばたたぬ)
- 商人に系図なし(あきんどにけいずなし)
- 商人の嘘は神もお許し(あきんどのうそはかみもおゆるし)
- 商人の子は算盤の音で目を覚ます(あきんどのこはそろばんのおとでめをさます)
- 商人の空値(あきんどのそらね)
- 商人の元値(あきんどのもとね)
- 商人は損していつか倉が建つ(あきんどはそんしていつかくらがたつ)
- 悪人あればこそ善人も顕る(あくにんあればこそぜんにんもあらわる)
「照」を含むことわざ
- 片山曇れば片山日照る(かたやまくもればかたやまひてる)
- 肝胆相照らす(かんたんあいてらす)
- ここばかりに日は照らぬ(ここばかりにひはてらぬ)
- 太陽の照っているうちに干し草を作れ(たいようのてっているうちにほしくさをつくれ)
- 破鏡再び照らさず(はきょうふたたびてらさず)
- 陽の照っているうちに干し草を作れ(ひのてっているうちにほしくさをつくれ)
- 明鏡も裏を照らさず(めいきょうもうらをてらさず)
- 落花枝に帰らず、破鏡再び照らさず(らっかえだにかえらず、はきょうふたたびてらさず)
- 落花枝に返らず、破鏡再び照らさず(らっかえだにかえらず、はきょうふたたびてらさず)
- 瑠璃も玻璃も照らせば光る(るりもはりもてらせばひかる)



