夏の虫、氷を笑うとは
夏の虫、氷を笑う
なつのむし、こおりをわらう
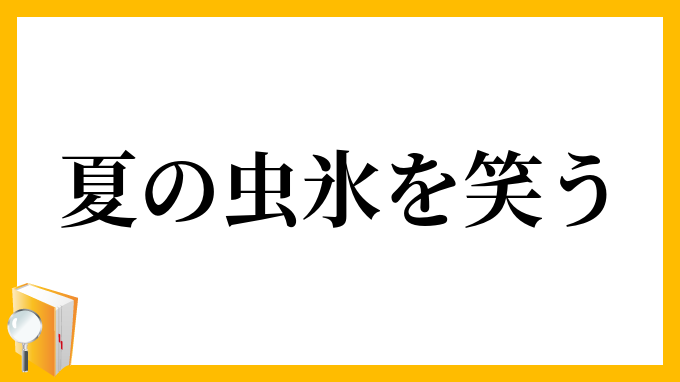
| 言葉 | 夏の虫、氷を笑う |
|---|---|
| 読み方 | なつのむし、こおりをわらう |
| 意味 | 見識が狭い者が偉そうにすることのたとえ。
夏の間だけ生きている虫は、氷が何なのかを知らないくせに氷を笑うとの意から。 「夏の虫、氷を知らず」ともいう。 |
| 異形 | 夏の虫、氷を知らず(なつのむし、こおりをしらず) |
| 場面用途 | 夏 / 季節 |
| 類句 | 井の中の蛙大海を知らず(いのなかのかわずたいかいをしらず) |
| 使用漢字 | 夏 / 虫 / 氷 / 笑 / 知 |
「夏」を含むことわざ
- 戴く物は夏も小袖(いただくものはなつもこそで)
- 仕事幽霊飯弁慶、その癖夏痩せ寒細り、たまたま肥ゆれば腫れ病(しごとゆうれいめしべんけい、そのくせなつやせかんぼそり、たまたまこゆればはれやまい)
- 天地、夏冬、雪と墨(てんち、なつふゆ、ゆきとすみ)
- 飛んで火に入る夏の虫(とんでひにいるなつのむし)
- 夏歌う者は冬泣く(なつうたうものはふゆなく)
- 夏布子の寒帷子(なつぬのこのかんかたびら)
- 夏の風邪は犬も食わぬ(なつのかぜはいぬもくわぬ)
- 夏の小袖(なつのこそで)
「虫」を含むことわざ
- 一寸の虫にも五分の魂(いっすんのむしにもごぶのたましい)
- 疳の虫が起こる(かんのむしがおこる)
- 獅子、身中の虫(しし、しんちゅうのむし)
- 小の虫を殺して大の虫を助ける(しょうのむしをころしてだいのむしをたすける)
- 蓼食う虫も好き好き(たでくうむしもすきずき)
- 蓼の虫は蓼で死ぬ(たでのむしはたででしぬ)
- 大の虫を生かして小の虫を殺す(だいのむしをいかしてしょうのむしをころす)
- 飛んで火に入る夏の虫(とんでひにいるなつのむし)
- 鳴く虫は捕らえられる(なくむしはとらえられる)
「氷」を含むことわざ
- 脂に画き、氷に鏤む(あぶらにえがき、こおりにちりばむ)
- 氷に鏤め、脂に描く(こおりにちりばめあぶらにえがく)
- 氷に鏤め、水に描く(こおりにちりばめみずにえがく)
- 氷は水より出でて水よりも寒し(こおりはみずよりいでてみずよりもさむし)
- 霜を履んで堅氷至る(しもをふんでけんぴょういたる)
- 小寒の氷大寒に解く(しょうかんのこおりだいかんにとく)
- 薄氷を履む(はくひょうをふむ)
- 薄氷を踏む(はくひょうをふむ)
「笑」を含むことわざ
- 朝のぴっかり姑の笑い(あさのぴっかりしゅうとめのわらい)
- 明日の事を言えば鬼が笑う(あすのことをいえばおにがわらう)
- 言い出しこき出し笑い出し(いいだしこきだしわらいだし)
- 怒れる拳、笑顔に当たらず(いかれるこぶし、えがおにあたらず)
- 一笑に付す(いっしょうにふす)
- 一笑に付する(いっしょうにふする)
- 一笑を買う(いっしょうをかう)
- 一銭を笑う者は一銭に泣く(いっせんをわらうものはいっせんになく)
- 今泣いた烏がもう笑う(いまないたからすがもうわらう)
- 今鳴いた烏がもう笑う(いまないたからすがもうわらう)



