氷は水より出でて水よりも寒しとは
氷は水より出でて水よりも寒し
こおりはみずよりいでてみずよりもさむし
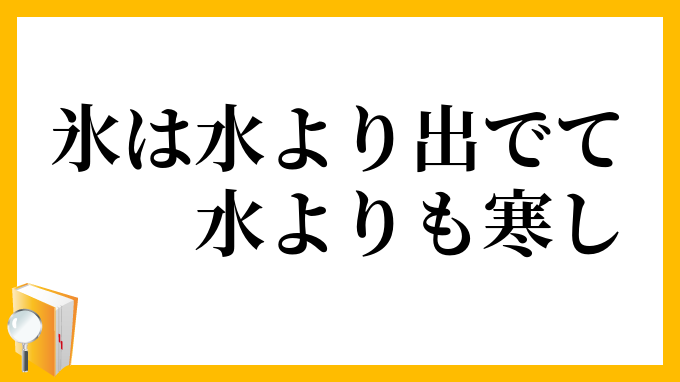
| 言葉 | 氷は水より出でて水よりも寒し |
|---|---|
| 読み方 | こおりはみずよりいでてみずよりもさむし |
| 意味 | 弟子が師よりも優れたものになることのたとえ。
水からできた氷が、水よりも冷たくなるとの意から。 |
| 出典 | 『荀子』 |
| 場面用途 | 師匠・弟子 |
| 類句 | 青は藍より出でて藍より青し(あおはあいよりいでてあいよりあおし) |
| 使用語彙 | より / よりも |
| 使用漢字 | 氷 / 水 / 出 / 寒 |
「氷」を含むことわざ
- 脂に画き、氷に鏤む(あぶらにえがき、こおりにちりばむ)
- 氷に鏤め、脂に描く(こおりにちりばめあぶらにえがく)
- 氷に鏤め、水に描く(こおりにちりばめみずにえがく)
- 霜を履んで堅氷至る(しもをふんでけんぴょういたる)
- 小寒の氷大寒に解く(しょうかんのこおりだいかんにとく)
- 夏の虫、氷を知らず(なつのむし、こおりをしらず)
- 夏の虫、氷を笑う(なつのむし、こおりをわらう)
- 薄氷を履むが如し(はくひょうをふむがごとし)
- 氷山の一角(ひょうざんのいっかく)
「水」を含むことわざ
- 明日食う塩辛に今日から水を飲む(あすくうしおからにきょうからみずをのむ)
- 汗水垂らす(あせみずたらす)
- 汗水流す(あせみずながす)
- 汗水を流す(あせみずをながす)
- 頭から水を浴びたよう(あたまからみずをあびたよう)
- 頭から水を掛けられたよう(あたまからみずをかけられたよう)
- 魚心あれば水心(うおごころあればみずごころ)
- 魚と水(うおとみず)
- 魚の水に離れたよう(うおのみずにはなれたよう)
- 魚の水を得たよう(うおのみずをえたよう)
「出」を含むことわざ
- 愛出ずる者は愛返り、福往く者は福来る(あいいずるものはあいかえり、ふくゆくものはふくきたる)
- 愛は小出しにせよ(あいはこだしにせよ)
- 青は藍より出でて藍より青し(あおはあいよりいでてあいよりあおし)
- 垢は擦るほど出る、あらは探すほど出る(あかはこするほどでる、あらはさがすほどでる)
- 明るみに出る(あかるみにでる)
- 顎を出す(あごをだす)
- 朝日が西から出る(あさひがにしからでる)
- 足が出る(あしがでる)
- 足を出す(あしをだす)
- 仇も情けも我が身より出る(あだもなさけもわがみよりでる)



