愛は小出しにせよとは
愛は小出しにせよ
あいはこだしにせよ
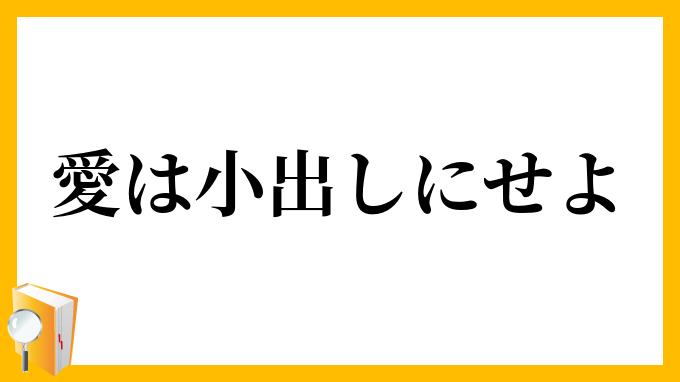
| 言葉 | 愛は小出しにせよ |
|---|---|
| 読み方 | あいはこだしにせよ |
| 意味 | 人を愛する時は、少しずつ長く続けるのがよいということ。 |
| 使用語彙 | 愛 / 小出し / 小 |
| 使用漢字 | 愛 / 小 / 出 |
「愛」を含むことわざ
- 愛出ずる者は愛返り、福往く者は福来る(あいいずるものはあいかえり、ふくゆくものはふくきたる)
- 愛多ければ憎しみ至る(あいおおければにくしみいたる)
- 愛嬌を振りまく(あいきょうをふりまく)
- 愛敬を振りまく(あいきょうをふりまく)
- 愛想が尽きる(あいそうがつきる)
- 愛想が尽きる(あいそがつきる)
- 愛想づかしも金から起きる(あいそづかしもかねからおきる)
- 愛想も小想も尽き果てる(あいそもこそもつきはてる)
- 愛想を尽かす(あいそをつかす)
- 愛立てないは祖母育ち(あいだてないはばばそだち)
「小」を含むことわざ
- 愛想も小想も尽き果てる(あいそもこそもつきはてる)
- 戴く物は夏も小袖(いただくものはなつもこそで)
- 因果の小車(いんがのおぐるま)
- 旨い物は小人数(うまいものはこにんずう)
- 大嘘はつくとも小嘘はつくな(おおうそはつくともこうそはつくな)
- 大木の下に小木育たず(おおきのしたにおぎそだたず)
- 大木の下に小木育つ(おおきのしたにおぎそだつ)
- 大遣いより小遣い(おおづかいよりこづかい)
- 大摑みより小摑み(おおづかみよりこづかみ)



