大木の下に小木育たずとは
大木の下に小木育たず
おおきのしたにおぎそだたず
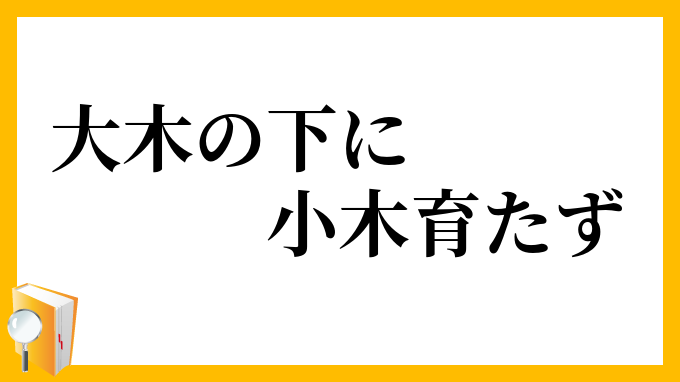
| 言葉 | 大木の下に小木育たず |
|---|---|
| 読み方 | おおきのしたにおぎそだたず |
| 意味 | 大きな権力の庇護の下では立派な人間は育ちにくいということ。
大きな木の下は採光や風通しが悪く、小さな木が育たないとの意から。 |
| 使用漢字 | 大 / 木 / 下 / 小 / 育 |
「大」を含むことわざ
- 阿保の大食い(あほのおおぐい)
- 諍いをしいしい腹を大きくし(いさかいをしいしいはらをおおきくし)
- 一木いずくんぞ能く大廈を支えん(いちぼくいずくんぞよくたいかをささえん)
- 一木大廈の崩るるを支うる能わず(いちぼくたいかのくずるるをささうるあたわず)
- 井の中の蛙大海を知らず(いのなかのかわずたいかいをしらず)
- 上を下への大騒ぎ(うえをしたへのおおさわぎ)
- 独活の大木(うどのたいぼく)
- 独活の大木柱にならぬ(うどのたいぼくはしらにならぬ)
- 瓜の皮は大名に剝かせよ、柿の皮は乞食に剝かせよ(うりのかわはだいみょうにむかせよ、かきのかわはこじきにむかせよ)
- 江戸っ子の往き大名還り乞食(えどっこのゆきだいみょうかえりこじき)
「木」を含むことわざ
- 足を擂り粉木にする(あしをすりこぎにする)
- 諍い果てての乳切り木(いさかいはててのちぎりぎ)
- 諍い果てての千切り木(いさかいはててのちぎりぎ)
- 石が流れて木の葉が沈む(いしがながれてこのはがしずむ)
- 一木いずくんぞ能く大廈を支えん(いちぼくいずくんぞよくたいかをささえん)
- 一木大廈の崩るるを支うる能わず(いちぼくたいかのくずるるをささうるあたわず)
- 移木の信(いぼくのしん)
- 植木屋の庭できが多い(うえきやのにわできがおおい)
- 植木屋の庭で気が多い(うえきやのにわできがおおい)
- 魚の木に登るが如し(うおのきにのぼるがごとし)
「下」を含むことわざ
- 敢えて天下の先とならず(あえててんかのさきとならず)
- 商い上手の仕入れ下手(あきないじょうずのしいれべた)
- 上げたり下げたり(あげたりさげたり)
- 足下から鳥が立つ(あしもとからとりがたつ)
- 足下につけ込む(あしもとにつけこむ)
- 足下に火が付く(あしもとにひがつく)
- 足下にも及ばない(あしもとにもおよばない)
- 足下にも寄りつけない(あしもとにもよりつけない)
- 足下の明るいうち(あしもとのあかるいうち)
- 足下へも寄り付けない(あしもとへもよりつけない)
「小」を含むことわざ
- 愛想も小想も尽き果てる(あいそもこそもつきはてる)
- 愛は小出しにせよ(あいはこだしにせよ)
- 戴く物は夏も小袖(いただくものはなつもこそで)
- 因果の小車(いんがのおぐるま)
- 旨い物は小人数(うまいものはこにんずう)
- 大嘘はつくとも小嘘はつくな(おおうそはつくともこうそはつくな)
- 大木の下に小木育つ(おおきのしたにおぎそだつ)
- 大遣いより小遣い(おおづかいよりこづかい)
- 大摑みより小摑み(おおづかみよりこづかみ)



