自慢は知恵の行き止まりとは
自慢は知恵の行き止まり
じまんはちえのいきどまり
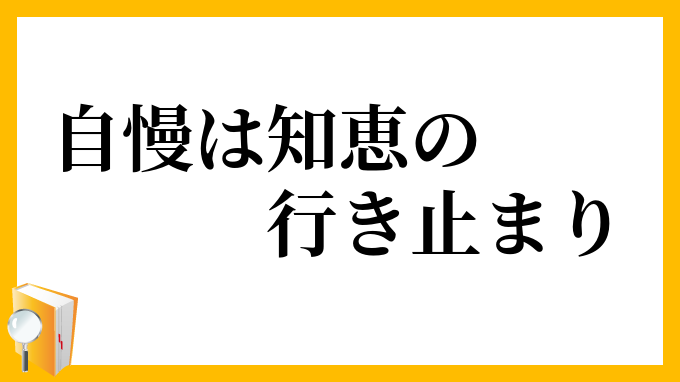
| 言葉 | 自慢は知恵の行き止まり |
|---|---|
| 読み方 | じまんはちえのいきどまり |
| 意味 | 自慢をするようになると、進歩はもう望めないということ。 |
| 使用語彙 | 自慢 / 行き止まり / 行き |
| 使用漢字 | 自 / 慢 / 知 / 恵 / 行 / 止 |
「自」を含むことわざ
- 相惚れ自惚れ片惚れ岡惚れ(あいぼれうぬぼれかたぼれおかぼれ)
- 医者の自脈効き目なし(いしゃのじみゃくききめなし)
- 医者よ自らを癒せ(いしゃよみずからをいやせ)
- 自惚れと瘡気のない者はない(うぬぼれとかさけのないものはない)
- 勝った自慢は負けての後悔(かったじまんはまけてのこうかい)
- 神は自ら助くる者を助く(かみはみずからたすくるものをたすく)
- 口自慢の仕事下手(くちじまんのしごとべた)
- 薫は香を以て自ら焼く(くんはこうをもってみずからやく)
- 怪我と弁当は自分持ち(けがとべんとうはじぶんもち)
- 剛戻自ら用う(ごうれいみずからもちう)
「慢」を含むことわざ
- 勝った自慢は負けての後悔(かったじまんはまけてのこうかい)
- 口自慢の仕事下手(くちじまんのしごとべた)
- 高慢は出世の行き止まり(こうまんはしゅっせのいきどまり)
- 自慢高慢、馬鹿のうち(じまんこうまん、ばかのうち)
- 自慢高慢酒の燗(じまんこうまんさけのかん)
- 自慢の糞は犬も食わぬ(じまんのくそはいぬもくわぬ)
- 卑下も自慢のうち(ひげもじまんのうち)
- 独り自慢の褒め手なし(ひとりじまんのほめてなし)
- 慢心鼻を弾かる(まんしんはなをはじかる)
「知」を含むことわざ
- 相対のことはこちゃ知らぬ(あいたいのことはこちゃしらぬ)
- 明日知らぬ世(あすしらぬよ)
- 過ちを観て斯に仁を知る(あやまちをみてここにじんをしる)
- 過ちを観て仁を知る(あやまちをみてじんをしる)
- 息の臭きは主知らず(いきのくさきはぬししらず)
- いざ知らず(いざしらず)
- 衣食足りて栄辱を知る(いしょくたりてえいじょくをしる)
- 衣食足りて礼節を知る(いしょくたりてれいせつをしる)
- 衣食足れば則ち栄辱を知る(いしょくたればすなわちえいじょくをしる)
- 一文惜しみの百知らず(いちもんおしみのひゃくしらず)
「恵」を含むことわざ
- 大男総身に知恵が回りかね(おおおとこそうみにちえがまわりかね)
- 女の知恵は鼻の先(おんなのちえははなのさき)
- 経験は知恵の父記憶の母(けいけんはちえのちちきおくのはは)
- 下種の後知恵(げすのあとぢえ)
- 下衆の後知恵(げすのあとぢえ)
- 後悔は知恵の緒(こうかいはちえのいとぐち)
- 小男の総身の知恵も知れたもの(こおとこのそうみのちえもしれたもの)
- 猿知恵(さるぢえ)
- 三人寄れば文殊の知恵(さんにんよればもんじゅのちえ)
「行」を含むことわざ
- 悪事、千里を行く(あくじせんりをいく)
- 畦から行くも田から行くも同じ(あぜからいくもたからいくもおなじ)
- 後へも先へも行かぬ(あとへもさきへもいかぬ)
- 好い線を行く(いいせんをいく)
- 言うと行うとは別問題である(いうとおこなうとはべつもんだいである)
- 言うは易く行うは難し(いうはやすくおこなうはかたし)
- 行き当たりばったり(いきあたりばったり)
- 行き掛けの駄賃(いきがけのだちん)
- 行く行くの長居り(いくいくのながおり)
- 往に跡へ行くとも死に跡へ行くな(いにあとへゆくともしにあとへゆくな)



