言うと行うとは別問題であるとは
言うと行うとは別問題である
いうとおこなうとはべつもんだいである
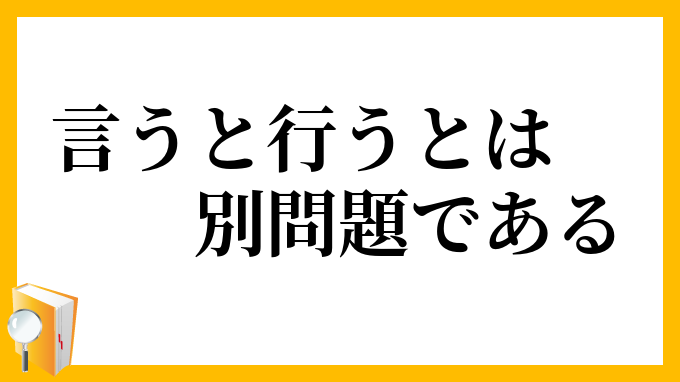
| 言葉 | 言うと行うとは別問題である |
|---|---|
| 読み方 | いうとおこなうとはべつもんだいである |
| 意味 | 口で言うことと、それを実行することとは別で、言葉通りに実践するのは難しいということ。 |
| 類句 | 言うは易く行うは難し(いうはやすくおこなうはかたし) |
| 使用語彙 | 言う / 行う |
| 使用漢字 | 言 / 行 / 別 / 問 / 題 |
「言」を含むことわざ
- ああ言えばこう言う(ああいえばこういう)
- 合言葉にする(あいことばにする)
- 呆れて物が言えない(あきれてものがいえない)
- 明日の事を言えば鬼が笑う(あすのことをいえばおにがわらう)
- あっと言う間(あっというま)
- あっと言わせる(あっといわせる)
- 後から剝げる正月言葉(あとからはげるしょうがつことば)
- 穴を掘って言い入れる(あなをほっていいいれる)
- 有り体に言う(ありていにいう)
- 言い得て妙(いいえてみょう)
「行」を含むことわざ
- 悪事、千里を行く(あくじせんりをいく)
- 畦から行くも田から行くも同じ(あぜからいくもたからいくもおなじ)
- 後へも先へも行かぬ(あとへもさきへもいかぬ)
- 好い線を行く(いいせんをいく)
- 言うは易く行うは難し(いうはやすくおこなうはかたし)
- 行き当たりばったり(いきあたりばったり)
- 行き掛けの駄賃(いきがけのだちん)
- 行く行くの長居り(いくいくのながおり)
- 往に跡へ行くとも死に跡へ行くな(いにあとへゆくともしにあとへゆくな)
「別」を含むことわざ
- 会うは別れの始め(あうはわかれのはじめ)
- 逢うは別れの始め(あうはわかれのはじめ)
- 思うに別れて思わぬに添う(おもうにわかれておもわぬにそう)
- 鎹分別(かすがいふんべつ)
- 酒に別腸あり(さけにべつちょうあり)
- 死に別れより生き別れ(しにわかれよりいきわかれ)
- 他人の別れ棒の端(たにんのわかれぼうのはし)
- 終の別れ(ついのわかれ)
- 年寄りの物忘れ、若者の無分別(としよりのものわすれ、わかもののむふんべつ)
「問」を含むことわざ
- 生きるべきか死すべきかそれが問題だ(いきるべきかしすべきかそれがもんだいだ)
- 一引き、二才、三学問(いちひき、にさい、さんがくもん)
- 田舎の学問より京の昼寝(いなかのがくもんよりきょうのひるね)
- 海の事は漁師に問え(うみのことはりょうしにとえ)
- 老いの学問(おいのがくもん)
- 鼎の軽重を問う(かなえのけいちょうをとう)
- 下問を恥じず(かもんをはじず)
- 学問に王道なし(がくもんにおうどうなし)
- 子供の根問い(こどものねどい)



