小寒の氷大寒に解くとは
小寒の氷大寒に解く
しょうかんのこおりだいかんにとく
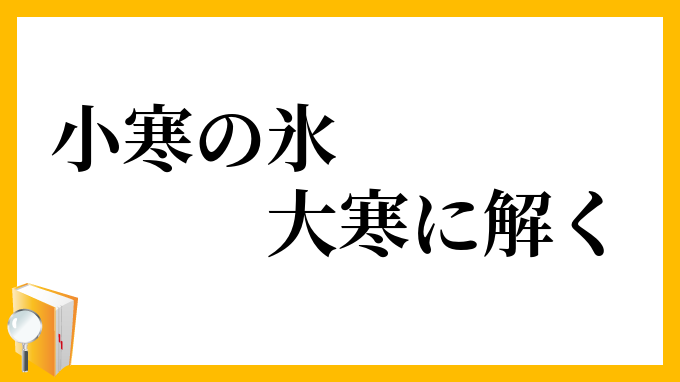
| 言葉 | 小寒の氷大寒に解く |
|---|---|
| 読み方 | しょうかんのこおりだいかんにとく |
| 意味 | 物事が必ず順に従って進むわけではないということのたとえ。
最も寒いはずの大寒が小寒よりも温かいとの意から。 |
| 使用語彙 | 小寒 |
| 使用漢字 | 小 / 寒 / 氷 / 大 / 解 |
「小」を含むことわざ
- 愛想も小想も尽き果てる(あいそもこそもつきはてる)
- 愛は小出しにせよ(あいはこだしにせよ)
- 戴く物は夏も小袖(いただくものはなつもこそで)
- 因果の小車(いんがのおぐるま)
- 旨い物は小人数(うまいものはこにんずう)
- 大嘘はつくとも小嘘はつくな(おおうそはつくともこうそはつくな)
- 大木の下に小木育たず(おおきのしたにおぎそだたず)
- 大木の下に小木育つ(おおきのしたにおぎそだつ)
- 大遣いより小遣い(おおづかいよりこづかい)
- 大摑みより小摑み(おおづかみよりこづかみ)
「寒」を含むことわざ
- 暑さ寒さも彼岸まで(あつささむさもひがんまで)
- 言うまいと思えど今朝の寒さかな(いうまいとおもえどけさのさむさかな)
- 医者寒からず儒者寒し(いしゃさむからずじゅしゃさむし)
- 遠慮ひだるし伊達寒し(えんりょひだるしだてさむし)
- お寒い(おさむい)
- 河童の寒稽古(かっぱのかんげいこ)
- 寒に帷子、土用に布子(かんにかたびら、どようにぬのこ)
- 唇滅びて歯寒し(くちびるほろびてはさむし)
- 賢者ひだるし、伊達寒し(けんじゃひだるし、だてさむし)
- 氷は水より出でて水よりも寒し(こおりはみずよりいでてみずよりもさむし)
「氷」を含むことわざ
- 脂に画き、氷に鏤む(あぶらにえがき、こおりにちりばむ)
- 氷に鏤め、脂に描く(こおりにちりばめあぶらにえがく)
- 氷に鏤め、水に描く(こおりにちりばめみずにえがく)
- 氷は水より出でて水よりも寒し(こおりはみずよりいでてみずよりもさむし)
- 霜を履んで堅氷至る(しもをふんでけんぴょういたる)
- 夏の虫、氷を知らず(なつのむし、こおりをしらず)
- 夏の虫、氷を笑う(なつのむし、こおりをわらう)
- 薄氷を履むが如し(はくひょうをふむがごとし)
- 氷山の一角(ひょうざんのいっかく)
「大」を含むことわざ
- 阿保の大食い(あほのおおぐい)
- 諍いをしいしい腹を大きくし(いさかいをしいしいはらをおおきくし)
- 一木いずくんぞ能く大廈を支えん(いちぼくいずくんぞよくたいかをささえん)
- 一木大廈の崩るるを支うる能わず(いちぼくたいかのくずるるをささうるあたわず)
- 井の中の蛙大海を知らず(いのなかのかわずたいかいをしらず)
- 上を下への大騒ぎ(うえをしたへのおおさわぎ)
- 独活の大木(うどのたいぼく)
- 独活の大木柱にならぬ(うどのたいぼくはしらにならぬ)
- 瓜の皮は大名に剝かせよ、柿の皮は乞食に剝かせよ(うりのかわはだいみょうにむかせよ、かきのかわはこじきにむかせよ)
- 江戸っ子の往き大名還り乞食(えどっこのゆきだいみょうかえりこじき)
「解」を含むことわざ
- 印綬を解く(いんじゅをとく)
- 頤を解く(おとがいをとく)
- 解語の花(かいごのはな)
- 小寒の氷大寒に解く(しょうかんのこおりだいかんにとく)
- 刃を迎えて解く(じんをむかえてとく)
- 理解に苦しむ(りかいにくるしむ)



