仕事幽霊飯弁慶、その癖夏痩せ寒細り、たまたま肥ゆれば腫れ病とは
仕事幽霊飯弁慶、その癖夏痩せ寒細り、たまたま肥ゆれば腫れ病
しごとゆうれいめしべんけい、そのくせなつやせかんぼそり、たまたまこゆればはれやまい
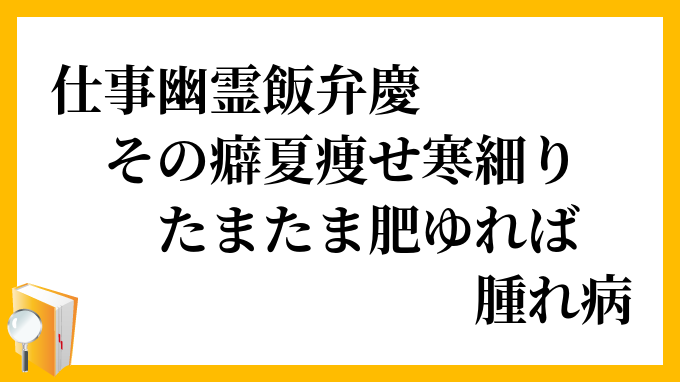
| 言葉 | 仕事幽霊飯弁慶、その癖夏痩せ寒細り、たまたま肥ゆれば腫れ病 |
|---|---|
| 読み方 | しごとゆうれいめしべんけい、そのくせなつやせかんぼそり、たまたまこゆればはれやまい |
| 意味 | 仕事は出来ないのに飯は山のように食べ、夏も冬のように痩せていて、たまに太ったかと思えば病気にかかっている。怠け者の大食漢の多病をあざけった言葉。 |
| 場面用途 | 食事 |
| 使用語彙 | 仕事 / 幽霊 / 飯 / 夏痩せ |
| 使用漢字 | 仕 / 事 / 幽 / 霊 / 飯 / 弁 / 慶 / 癖 / 夏 / 痩 / 寒 / 細 / 肥 / 腫 / 病 |
「仕」を含むことわざ
- 商い上手の仕入れ下手(あきないじょうずのしいれべた)
- 口自慢の仕事下手(くちじまんのしごとべた)
- 芸が身を助けるほどの不仕合わせ(げいがみをたすけるほどのふしあわせ)
- 恋は仕勝ち(こいはしがち)
- 細工は流々、仕上げをご覧じろ(さいくはりゅうりゅう、しあげをごろうじろ)
- 細工は流流、仕上げをご覧じろ(さいくはりゅうりゅう、しあげをごろうじろ)
- 仕上げが肝心(しあげがかんじん)
- すまじきものは宮仕え(すまじきものはみやづかえ)
- 急いては事を仕損じる(せいてはことをしそんじる)
「事」を含むことわざ
- 秋葉山から火事(あきばさんからかじ)
- 悪事、千里を走る(あくじ、せんりをはしる)
- 悪事、身にかえる(あくじ、みにかえる)
- 悪事、千里を行く(あくじせんりをいく)
- 悪は一旦の事なり(あくはいったんのことなり)
- 明日の事は明日案じよ(あすのことはあすあんじよ)
- 明日の事を言えば鬼が笑う(あすのことをいえばおにがわらう)
- 当て事と畚褌は先から外れる(あてことともっこふんどしはさきからはずれる)
- 当て事と越中褌は向こうから外れる(あてごととえっちゅうふんどしはむこうからはずれる)
- 当て事は向こうから外れる(あてごとはむこうからはずれる)
「幽」を含むことわざ
- 仕事幽霊飯弁慶、その癖夏痩せ寒細り、たまたま肥ゆれば腫れ病(しごとゆうれいめしべんけい、そのくせなつやせかんぼそり、たまたまこゆればはれやまい)
- 幽明境を異にする(ゆうめいさかいをことにする)
- 幽明処を隔つ(ゆうめいところをへだつ)
- 幽霊の正体見たり枯れ尾花(ゆうれいのしょうたいみたりかれおばな)
「霊」を含むことわざ
- 仕事幽霊飯弁慶、その癖夏痩せ寒細り、たまたま肥ゆれば腫れ病(しごとゆうれいめしべんけい、そのくせなつやせかんぼそり、たまたまこゆればはれやまい)
- 天才とは一パーセントの霊感と九十九パーセントの汗である(てんさいとはいちぱーせんとのれいかんときゅうじゅうきゅうぱーせんとのあせである)
- 幽霊の正体見たり枯れ尾花(ゆうれいのしょうたいみたりかれおばな)
「飯」を含むことわざ
- 朝飯前(あさめしまえ)
- 朝飯前のお茶漬け(あさめしまえのおちゃづけ)
- ある時は米の飯(あるときはこめのめし)
- いつも月夜に米の飯(いつもつきよにこめのめし)
- 同じ釜の飯を食う(おなじかまのめしをくう)
- 思し召しより米の飯(おぼしめしよりこめのめし)
- 臭い飯を食う(くさいめしをくう)
- 食わぬ飯が髭に付く(くわぬめしがひげにつく)
- 米の飯と女は白いほどよい(こめのめしとおんなはしろいほどよい)
- 米の飯と天道様はどこへ行っても付いて回る(こめのめしとてんとうさまはどこへいってもついてまわる)
「弁」を含むことわざ
- 後ろ弁天、前不動(うしろべんてん、まえふどう)
- 内弁慶(うちべんけい)
- 内弁慶外すばり(うちべんけいそとすばり)
- 陰弁慶(かげべんけい)
- 口弁慶(くちべんけい)
- 怪我と弁当は自分持ち(けがとべんとうはじぶんもち)
- 懸河の弁(けんがのべん)
- 堅白同異の弁(けんぱくどういのべん)
- 黒白を弁せず(こくびゃくをべんせず)
「慶」を含むことわざ
- 内弁慶(うちべんけい)
- 内弁慶外すばり(うちべんけいそとすばり)
- 陰弁慶(かげべんけい)
- 口弁慶(くちべんけい)
- 積善の家には必ず余慶あり(せきぜんのいえにはかならずよけいあり)
- 弁慶に薙刀(べんけいになぎなた)
- 弁慶の立ち往生(べんけいのたちおうじょう)
- 弁慶の泣き所(べんけいのなきどころ)
「癖」を含むことわざ
- 厭じゃ厭じゃは女の癖(いやじゃいやじゃはおんなのくせ)
- 煙霞の癖(えんかのへき)
- 手癖が悪い(てくせがわるい)
- 手癖が悪い(てぐせがわるい)
- 無い物食おうが人の癖(ないものくおうがひとのくせ)
- 無くて七癖(なくてななくせ)
- 無くて七癖、有って四十八癖(なくてななくせ、あってしじゅうはっくせ)
- 難癖を付ける(なんくせをつける)
- 難無くして七癖(なんなくしてななくせ)
「夏」を含むことわざ
- 戴く物は夏も小袖(いただくものはなつもこそで)
- 天地、夏冬、雪と墨(てんち、なつふゆ、ゆきとすみ)
- 飛んで火に入る夏の虫(とんでひにいるなつのむし)
- 夏歌う者は冬泣く(なつうたうものはふゆなく)
- 夏布子の寒帷子(なつぬのこのかんかたびら)
- 夏の風邪は犬も食わぬ(なつのかぜはいぬもくわぬ)
- 夏の小袖(なつのこそで)
- 夏の虫、氷を知らず(なつのむし、こおりをしらず)
- 夏の虫、氷を笑う(なつのむし、こおりをわらう)
「痩」を含むことわざ
- 家の前の痩せ犬(うちのまえのやせいぬ)
- 猫が肥えれば鰹節が痩せる(ねこがこえればかつおぶしがやせる)
- 痩せ腕にも骨(やせうでにもほね)
- 痩せ馬に重荷(やせうまにおもに)
- 痩せ馬鞭を恐れず(やせうまむちをおそれず)
- 痩せ我慢は貧から起こる(やせがまんはひんからおこる)
- 痩せても枯れても(やせてもかれても)
- 痩せの大食い(やせのおおぐい)
- 痩せ法師の酢好み(やせほうしのすごのみ)
「寒」を含むことわざ
- 暑さ寒さも彼岸まで(あつささむさもひがんまで)
- 言うまいと思えど今朝の寒さかな(いうまいとおもえどけさのさむさかな)
- 医者寒からず儒者寒し(いしゃさむからずじゅしゃさむし)
- 遠慮ひだるし伊達寒し(えんりょひだるしだてさむし)
- お寒い(おさむい)
- 河童の寒稽古(かっぱのかんげいこ)
- 寒に帷子、土用に布子(かんにかたびら、どようにぬのこ)
- 唇滅びて歯寒し(くちびるほろびてはさむし)
- 賢者ひだるし、伊達寒し(けんじゃひだるし、だてさむし)
- 氷は水より出でて水よりも寒し(こおりはみずよりいでてみずよりもさむし)
「細」を含むことわざ
- 委細構わず(いさいかまわず)
- 河海は細流を択ばず(かかいはさいりゅうをえらばず)
- 芸が細かい(げいがこまかい)
- 子宝、脛が細る(こだから、すねがほそる)
- 細工は流々、仕上げをご覧じろ(さいくはりゅうりゅう、しあげをごろうじろ)
- 細工は流流、仕上げをご覧じろ(さいくはりゅうりゅう、しあげをごろうじろ)
- 細工貧乏人宝(さいくびんぼうひとだから)
- 細大漏らさず(さいだいもらさず)
- 子細に及ばず(しさいにおよばず)
「肥」を含むことわざ
- 秋高く馬肥ゆ(あきたかくうまこゆ)
- 口が肥える(くちがこえる)
- 座禅組むより肥やし汲め(ざぜんくむよりこやしくめ)
- 舌が肥える(したがこえる)
- 私腹を肥やす(しふくをこやす)
- 天高く馬肥ゆ(てんたかくうまこゆ)
- 天高く馬肥ゆる秋(てんたかくうまこゆるあき)
- 猫が肥えれば鰹節が痩せる(ねこがこえればかつおぶしがやせる)
- 二十過ぎての意見と彼岸過ぎての肥はきかぬ(はたちすぎてのいけんとひがんすぎてのこえはきかぬ)
「腫」を含むことわざ
- 仕事幽霊飯弁慶、その癖夏痩せ寒細り、たまたま肥ゆれば腫れ病(しごとゆうれいめしべんけい、そのくせなつやせかんぼそり、たまたまこゆればはれやまい)
- 出物腫れ物、所嫌わず(でものはれもの、ところきらわず)
- 腫れ物に触るよう(はれものにさわるよう)
- 惚れた腫れたは当座のうち(ほれたはれたはとうざのうち)



