弁慶の立ち往生とは
弁慶の立ち往生
べんけいのたちおうじょう
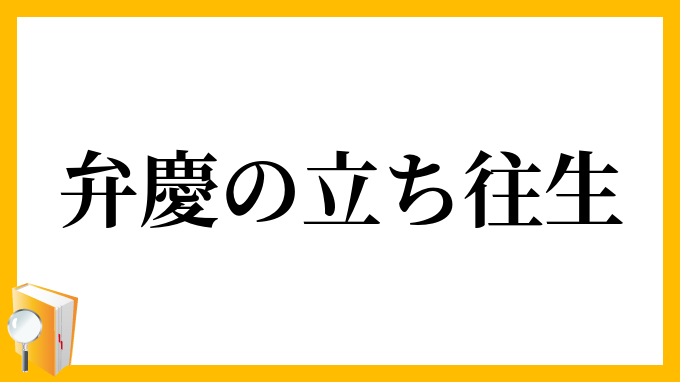
| 言葉 | 弁慶の立ち往生 |
|---|---|
| 読み方 | べんけいのたちおうじょう |
| 意味 | 進むことも退くこともできない状態のたとえ。源義経の家来の弁慶が、衣川の合戦で義経をかばって矢を受け、立ったまま死んだという伝説から。 |
| 使用語彙 | 往生 |
| 使用漢字 | 弁 / 慶 / 立 / 往 / 生 |
「弁」を含むことわざ
- 後ろ弁天、前不動(うしろべんてん、まえふどう)
- 内弁慶(うちべんけい)
- 内弁慶外すばり(うちべんけいそとすばり)
- 陰弁慶(かげべんけい)
- 口弁慶(くちべんけい)
- 怪我と弁当は自分持ち(けがとべんとうはじぶんもち)
- 懸河の弁(けんがのべん)
- 堅白同異の弁(けんぱくどういのべん)
- 黒白を弁せず(こくびゃくをべんせず)
- 仕事幽霊飯弁慶、その癖夏痩せ寒細り、たまたま肥ゆれば腫れ病(しごとゆうれいめしべんけい、そのくせなつやせかんぼそり、たまたまこゆればはれやまい)
「慶」を含むことわざ
- 内弁慶(うちべんけい)
- 内弁慶外すばり(うちべんけいそとすばり)
- 陰弁慶(かげべんけい)
- 口弁慶(くちべんけい)
- 仕事幽霊飯弁慶、その癖夏痩せ寒細り、たまたま肥ゆれば腫れ病(しごとゆうれいめしべんけい、そのくせなつやせかんぼそり、たまたまこゆればはれやまい)
- 積善の家には必ず余慶あり(せきぜんのいえにはかならずよけいあり)
- 弁慶に薙刀(べんけいになぎなた)
- 弁慶の泣き所(べんけいのなきどころ)
「立」を含むことわざ
- 愛立てないは祖母育ち(あいだてないはばばそだち)
- 間に立つ(あいだにたつ)
- 青筋を立てる(あおすじをたてる)
- 証を立てる(あかしをたてる)
- 秋風が立つ(あきかぜがたつ)
- 商人と屏風は直ぐには立たぬ(あきんどとびょうぶはすぐにはたたぬ)
- 足下から鳥が立つ(あしもとからとりがたつ)
- 頭から湯気を立てる(あたまからゆげをたてる)
- あちら立てればこちらが立たぬ(あちらたてればこちらがたたぬ)
- 石に立つ矢(いしにたつや)
「往」を含むことわざ
- 愛出ずる者は愛返り、福往く者は福来る(あいいずるものはあいかえり、ふくゆくものはふくきたる)
- 往に跡へ行くとも死に跡へ行くな(いにあとへゆくともしにあとへゆくな)
- 江戸っ子の往き大名還り乞食(えどっこのゆきだいみょうかえりこじき)
- 往時渺茫としてすべて夢に似たり(おうじびょうぼうとしてすべてゆめににたり)
- 往生際が悪い(おうじょうぎわがわるい)
- 既往は咎めず(きおうはとがめず)
- 商売往来にない商売(しょうばいおうらいにないしょうばい)
- 千万人と雖も吾往かん(せんまんにんといえどもわれゆかん)
- 善人なおもて往生を遂ぐ、況んや悪人をや(ぜんにんなおもておうじょうをとぐ、いわんやあくにんをや)
- 立ち往生する(たちおうじょうする)



