意志のある所には道があるとは
意志のある所には道がある
いしのあるところにはみちがある
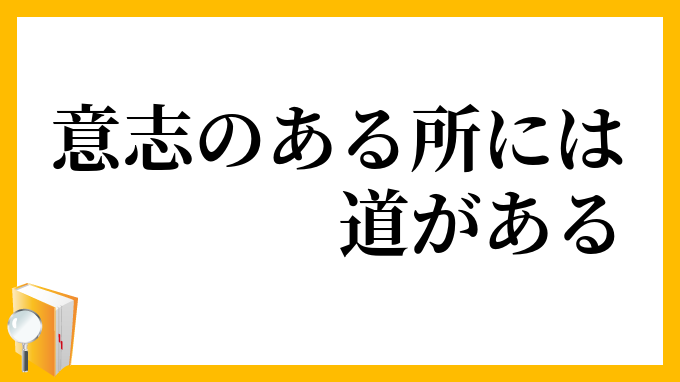
| 言葉 | 意志のある所には道がある |
|---|---|
| 読み方 | いしのあるところにはみちがある |
| 意味 | 実現しようという意志があれば、できないことはないというたとえ。 |
| 類句 | 思う念力、岩をも徹す(おもうねんりき、いわをもとおす) |
| 一念、天に通ず(いちねん、てんにつうず) | |
| 念力岩をも徹す(ねんりきいわをもとおす) | |
| 一心岩をも通す(いっしんいわをもとおす) | |
| 石に立つ矢(いしにたつや) | |
| 精神一到、何事か成らざらん(せいしんいっとう、なにごとかならざらん) | |
| 蟻の思いも天に届く(ありのおもいもてんにとどく) | |
| 雨垂れ石を穿つ(あまだれいしをうがつ) | |
| 点滴、石を穿つ | |
| 為せば成る(なせばなる) | |
| 使用語彙 | 意志 |
| 使用漢字 | 意 / 志 / 所 / 道 |
「意」を含むことわざ
- 意到りて筆随う(いいたりてふでしたがう)
- 意気が揚がる(いきがあがる)
- 意気天を衝く(いきてんをつく)
- 意気投合する(いきとうごうする)
- 意気に感じる(いきにかんじる)
- 意気に燃える(いきにもえる)
- 意気地がない(いくじがない)
- 意見と餅はつくほど練れる(いけんともちはつくほどねれる)
- 意地が汚い(いじがきたない)
「志」を含むことわざ
- 燕雀安んぞ鴻鵠の志を知らんや(えんじゃくいずくんぞこうこくのこころざしをしらんや)
- 鴻鵠の志(こうこくのこころざし)
- 志ある者は事竟に成る(こころざしあるものはことついになる)
- 志は髪の筋(こころざしはかみのすじ)
- 志は木の葉に包む(こころざしはこのはにつつむ)
- 済世の志(さいせいのこころざし)
- 三軍も帥を奪うべきなり、匹夫も志を奪うべからず(さんぐんもすいをうばうべきなり、ひっぷもこころざしをうばうべからず)
- 志学(しがく)
- 志士苦心多し(ししくしんおおし)
「所」を含むことわざ
- 余す所なく(あますところなく)
- 過ちは好む所にあり(あやまちはこのむところにあり)
- 痛い所をつく(いたいところをつく)
- 意のある所(いのあるところ)
- 柄のない所に柄をすげる(えのないところにえをすげる)
- 選ぶ所がない(えらぶところがない)
- 大所の犬になるとも小所の犬になるな(おおどころのいぬになるともこどころのいぬになるな)
- 己の欲する所を人に施せ(おのれのほっするところをひとにほどこせ)
- 己の欲せざる所は人に施すこと勿れ(おのれのほっせざるところはひとにほどこすことなかれ)



