鼬の道切りとは
鼬の道切り
いたちのみちきり
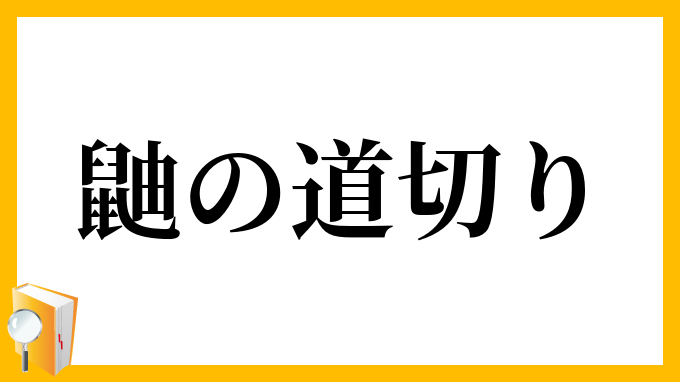
| 言葉 | 鼬の道切り |
|---|---|
| 読み方 | いたちのみちきり |
| 意味 | 交際や音信が途絶えることのたとえ。
鼬(イタチ)は一度通った道は二度と通らないといわれることから。 「鼬の道を切る」「鼬の道が切れる」「鼬の道」ともいう。 |
| 異形 | 鼬の道を切る(いたちのみちをきる) |
| 鼬の道が切れる(いたちのみちがきれる) | |
| 鼬の道(いたちのみち) | |
| 使用漢字 | 鼬 / 道 / 切 |
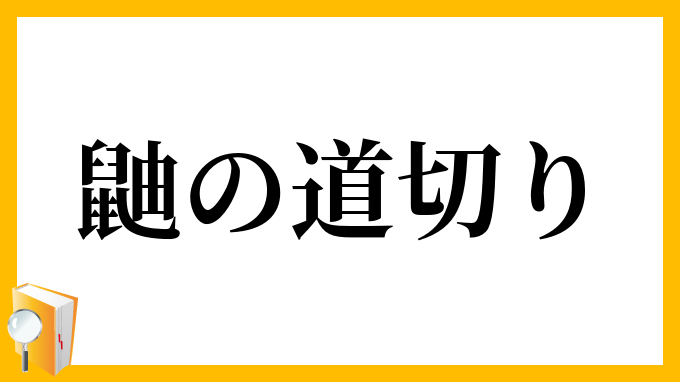
| 言葉 | 鼬の道切り |
|---|---|
| 読み方 | いたちのみちきり |
| 意味 | 交際や音信が途絶えることのたとえ。
鼬(イタチ)は一度通った道は二度と通らないといわれることから。 「鼬の道を切る」「鼬の道が切れる」「鼬の道」ともいう。 |
| 異形 | 鼬の道を切る(いたちのみちをきる) |
| 鼬の道が切れる(いたちのみちがきれる) | |
| 鼬の道(いたちのみち) | |
| 使用漢字 | 鼬 / 道 / 切 |