高きに登るには低きよりすとは
高きに登るには低きよりす
たかきにのぼるにはひくきよりす
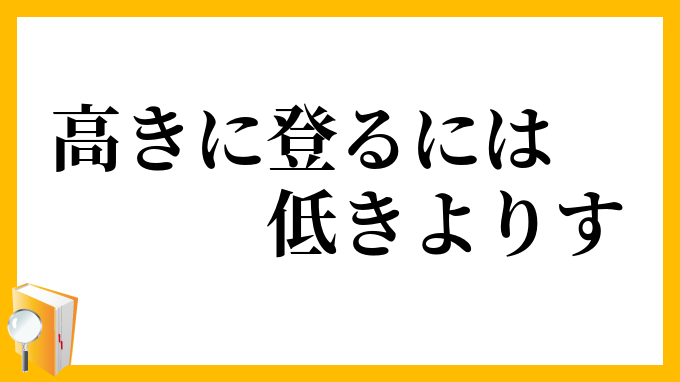
| 言葉 | 高きに登るには低きよりす |
|---|---|
| 読み方 | たかきにのぼるにはひくきよりす |
| 意味 | 物事には順序があり、手近なところから確実に始めるべきだということ。 |
| 出典 | 『中庸』 |
| 類句 | 千里の道も一歩から(せんりのみちもいっぽから) |
| 千里の行も足下より始まる | |
| 使用語彙 | より |
| 使用漢字 | 高 / 登 / 低 |
「高」を含むことわざ
- 秋高く馬肥ゆ(あきたかくうまこゆ)
- 空樽は音が高い(あきだるはおとがたかい)
- お高くとまる(おたかくとまる)
- お高く止まる(おたかくとまる)
- お高く留まる(おたかくとまる)
- 隠密の沙汰は高く言え(おんみつのさたはたかくいえ)
- 勘定高い(かんじょうだかい)
- 気位が高い(きぐらいがたかい)
- 食わず貧楽高枕(くわずひんらくたかまくら)
- 計算高い(けいさんだかい)
「登」を含むことわざ
- 魚の木に登るが如し(うおのきにのぼるがごとし)
- 鰻登り(うなぎのぼり)
- 及ばぬ鯉の滝登り(およばぬこいのたきのぼり)
- 木登りは木で果てる(きのぼりはきではてる)
- 鯉の滝登り(こいのたきのぼり)
- 猿に木登り(さるにきのぼり)
- 猿の水練、魚の木登り(さるのすいれん、うおのきのぼり)
- 船頭多くして、船、山へ登る(せんどうおおくして、ふね、やまへのぼる)
- 頼むと頼まれては犬も木へ登る(たのむとたのまれてはいぬもきへのぼる)
「低」を含むことわざ
- 頭が低い(あたまがひくい)
- 腰が低い(こしがひくい)
- 辞を低くする(じをひくくする)
- 高きに登るには低きよりす(たかきにのぼるにはひくきよりす)
- 低き所に水溜まる(ひくきところにみずたまる)
- 水の低きに就くが如し(みずのひくきにつくがごとし)



