家柄より芋茎とは
家柄より芋茎
いえがらよりいもがら
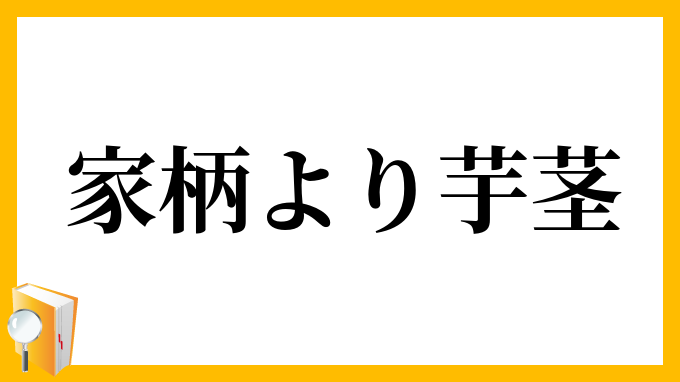
| 言葉 | 家柄より芋茎 |
|---|---|
| 読み方 | いえがらよりいもがら |
| 意味 | 良い家柄より、食べられる芋がらの方が値打ちがあるということ。「家柄」と「芋茎」の語呂合わせで、落ちぶれた名家をあざける言葉。 |
| 異形 | 家柄よりも芋茎(いえがらよりもいもがら) |
| 類句 | お家がらがら(おいえがらがら) |
| 使用語彙 | 家柄 / より |
| 使用漢字 | 家 / 柄 / 芋 / 茎 |
「家」を含むことわざ
- 空き家で声嗄らす(あきやでこえからす)
- 空き家の雪隠(あきやのせっちん)
- 家鴨も鴨の気位(あひるもかものきぐらい)
- 家売れば釘の価(いえうればくぎのあたい)
- 家給し人足る(いえきゅうしひとたる)
- 家に杖つく(いえにつえつく)
- 家に女房なきは火のない炉のごとし(いえににょうぼうなきはひのないろのごとし)
- 家に鼠、国に盗人(いえにねずみ、くににぬすびと)
- 家貧しくして孝子顕る(いえまずしくしてこうしあらわる)
「柄」を含むことわざ
- 柄のない所に柄をすげる(えのないところにえをすげる)
- 柄にもない(がらにもない)
- 采柄を握る(さいづかをにぎる)
- 百姓の泣き言と医者の手柄話(ひゃくしょうのなきごとといしゃのてがらばなし)
- 昔取った杵柄(むかしとったきねづか)
- 藪医者の手柄話(やぶいしゃのてがらばなし)
「芋」を含むことわざ
- 芋頭でも頭は頭(いもがしらでもかしらはかしら)
- 芋幹で足を衝く(いもがらであしをつく)
- 芋蔓式(いもづるしき)
- 芋の煮えたも御存じない(いものにえたもごぞんじない)
- 芋を洗うよう(いもをあらうよう)
- 蕪は鶉となり、山芋は鰻となる(かぶらはうずらとなり、やまいもはうなぎとなる)
- 擂り粉木で芋を盛る(すりこぎでいもをもる)
- 名主の跡は芋畑(なぬしのあとはいもばたけ)
- 塗り箸で芋を盛る(ぬりばしでいもをもる)
「茎」を含むことわざ
- 家柄より芋茎(いえがらよりいもがら)
- 芋茎で足を突く(いもがらであしをつく)



