揺り籠から墓場までとは
揺り籠から墓場まで
ゆりかごからはかばまで
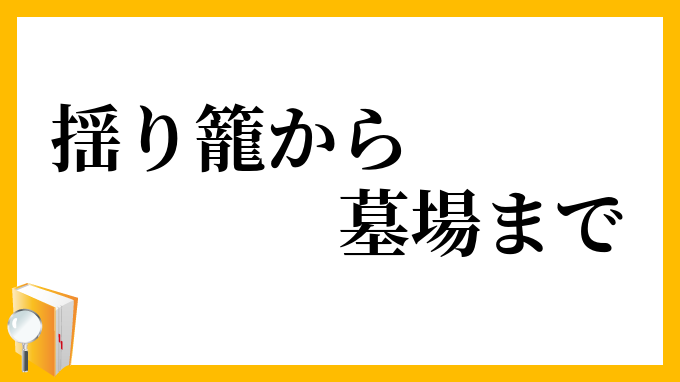
| 言葉 | 揺り籠から墓場まで |
|---|---|
| 読み方 | ゆりかごからはかばまで |
| 意味 | 生まれてから死ぬまでの一生のこと。イギリスの労働党が、第二次世界大戦後に唱えた社会保障政策のスローガン。 |
| 使用語彙 | 揺り籠 / 墓場 / 墓 |
| 使用漢字 | 揺 / 籠 / 墓 / 場 |
「揺」を含むことわざ
- 揺り籠から墓場まで(ゆりかごからはかばまで)
- 揺籃の地(ようらんのち)
「籠」を含むことわざ
- 陰に籠もる(いんにこもる)
- 駕籠舁き駕籠に乗らず(かごかきかごにのらず)
- 籠で水を汲む(かごでみずをくむ)
- 駕籠に乗る人担ぐ人、そのまた草鞋を作る人(かごにのるひとかつぐひと、そのまたわらじをつくるひと)
- 籠の鳥、雲を慕う(かごのとり、くもをしたう)
- 殻に籠る(からにこもる)
- 殻に閉じ籠もる(からにとじこもる)
- 自家薬籠中の物(じかやくろうちゅうのもの)
- 薬籠中の物(やくろうちゅうのもの)
「墓」を含むことわざ
- 墓穴を掘る(ぼけつをほる)
- 揺り籠から墓場まで(ゆりかごからはかばまで)



