夢寐にも忘れないとは
夢寐にも忘れない
むびにもわすれない
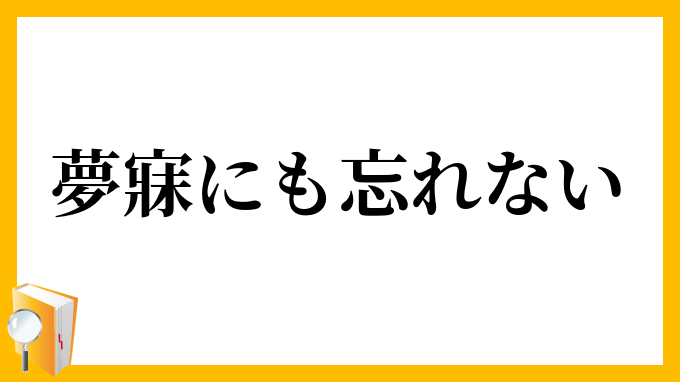
| 言葉 | 夢寐にも忘れない |
|---|---|
| 読み方 | むびにもわすれない |
| 意味 | ほんのわずかな間も忘れないということ。
「寐」は眠ること。 眠って夢を見ている間も忘れないとの意から。 |
| 使用語彙 | 夢寐 |
| 使用漢字 | 夢 / 寐 / 忘 |
「夢」を含むことわざ
- 一場の春夢(いちじょうのしゅんむ)
- 一炊の夢(いっすいのゆめ)
- 浮世は夢(うきよはゆめ)
- 栄華の夢(えいがのゆめ)
- 往時渺茫としてすべて夢に似たり(おうじびょうぼうとしてすべてゆめににたり)
- 槐安の夢(かいあんのゆめ)
- 槐夢(かいむ)
- 邯鄲の夢(かんたんのゆめ)
- 京の夢、大阪の夢(きょうのゆめ、おおさかのゆめ)
- 槿花一朝の夢(きんかいっちょうのゆめ)
「寐」を含むことわざ
- 夢寐にも忘れない(むびにもわすれない)



