鯉の一跳ねとは
鯉の一跳ね
こいのひとはね
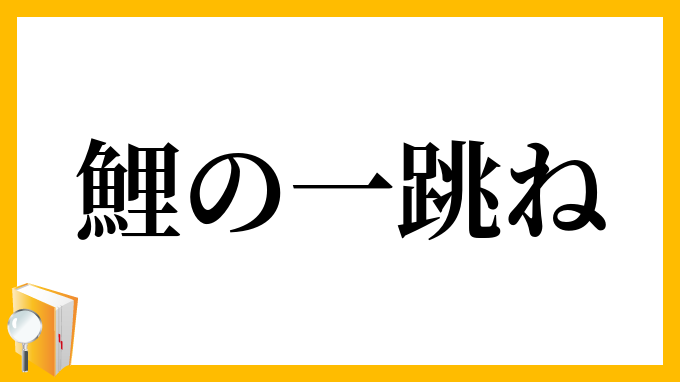
| 言葉 | 鯉の一跳ね |
|---|---|
| 読み方 | こいのひとはね |
| 意味 | 諦めがいいこと。潔いこと。捕らえられた鯉は一度跳ねるだけで、あとはじたばたしないという意味から。 |
| 使用語彙 | 鯉 / 一 |
| 使用漢字 | 鯉 / 一 / 跳 |
「鯉」を含むことわざ
- 生簀の鯉(いけすのこい)
- 江戸っ子は五月の鯉の吹き流し(えどっこはさつきのこいのふきながし)
- 及ばぬ鯉の滝登り(およばぬこいのたきのぼり)
- 鯉口を切る(こいぐちをきる)
- 鯉の滝登り(こいのたきのぼり)
- 俎上の鯉(そじょうのこい)
- 麦飯で鯉を釣る(むぎめしでこいをつる)
「一」を含むことわざ
- 悪は一旦の事なり(あくはいったんのことなり)
- 朝顔の花一時(あさがおのはなひととき)
- 朝の一時は晩の二時に当たる(あさのひとときはばんのふたときにあたる)
- 薊の花も一盛り(あざみのはなもひとさかり)
- あの世の千日、この世の一日(あのよのせんにち、このよのいちにち)
- 危ない橋も一度は渡れ(あぶないはしもいちどはわたれ)
- 粟一粒は汗一粒(あわひとつぶはあせひとつぶ)
- 板子一枚下は地獄(いたごいちまいしたはじごく)
- 一瓜実に二丸顔(いちうりざねににまるがお)
- 一応も二応も(いちおうもにおうも)
「跳」を含むことわざ
- 鯉の一跳ね(こいのひとはね)
- 千里一跳ね(せんりひとはね)
- 跳ぶ前に見よ(とぶまえにみよ)



