避けて通せ酒の酔いとは
避けて通せ酒の酔い
よけてとおせさけのよい
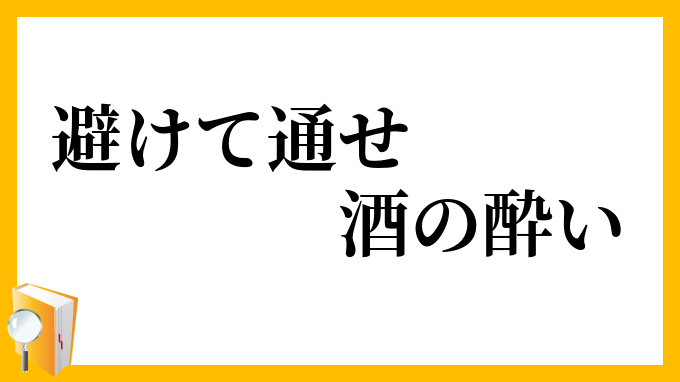
| 言葉 | 避けて通せ酒の酔い |
|---|---|
| 読み方 | よけてとおせさけのよい |
| 意味 | 酔っ払いには、かかわらないほうがよいということ。 |
| 使用漢字 | 避 / 通 / 酒 / 酔 |
「避」を含むことわざ
- 三舎を避く(さんしゃをさく)
- 断じて行えば鬼神も之を避く(だんじておこなえばきしんもこれをさく)
- 火を避けて水に陥る(ひをさけてみずにおちいる)
- 避けて通せ酒の酔い(よけてとおせさけのよい)
「通」を含むことわざ
- 息が通う(いきがかよう)
- 意地を通す(いじをとおす)
- 一芸は道に通ずる(いちげいはみちにつうずる)
- 一念、天に通ず(いちねん、てんにつうず)
- 一脈相通ずる(いちみゃくあいつうずる)
- 一脈通ずる(いちみゃくつうずる)
- 一心岩を通す(いっしんいわをとおす)
- 一心岩をも通す(いっしんいわをもとおす)
- 慇懃を通じる(いんぎんをつうじる)
- 慇懃を通ずる(いんぎんをつうずる)
「酒」を含むことわざ
- 赤いは酒の咎(あかいはさけのとが)
- 朝酒は門田を売っても飲め(あさざけはかどたをうってものめ)
- 新しい酒は新しい革袋に盛れ(あたらしいさけはあたらしいかわぶくろにもれ)
- 新しい酒を古い革袋に盛る(あたらしいさけをふるいかわぶくろにもる)
- 新しき葡萄酒は新しき革袋に入れよ(あたらしきぶどうしゅはあたらしきかわぶくろにいれよ)
- 一杯は人酒を飲む、二杯は酒酒を飲む、三杯は酒人を飲む(いっぱいはひとさけをのむ、にはいはさけさけをのむ、さんばいはさけひとをのむ)
- 後ろに柱前に酒(うしろにはしらまえにさけ)
- お情けより樽の酒(おなさけよりたるのさけ)
- 御神酒上がらぬ神はない(おみきあがらぬかみはない)
- 親の意見と冷や酒は後で利く(おやのいけんとひやざけはあとできく)



