御神酒上がらぬ神はないとは
御神酒上がらぬ神はない
おみきあがらぬかみはない
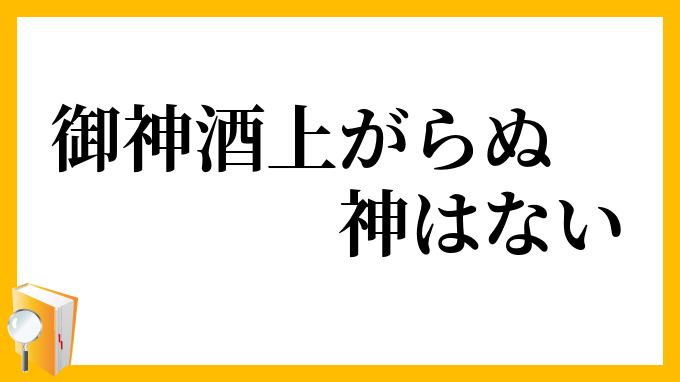
| 言葉 | 御神酒上がらぬ神はない |
|---|---|
| 読み方 | おみきあがらぬかみはない |
| 意味 | 神様でさえお酒を召し上がるのだから、人間が酒を飲むのは当たり前だということ。
酒飲みが飲酒することの自己弁護に使う言葉。 「御神酒」は、神前に供える酒のこと。 |
| 使用語彙 | 御神酒 / 神 |
| 使用漢字 | 御 / 神 / 酒 / 上 |
「御」を含むことわざ
- 晏子の御(あんしのぎょ)
- 芋の煮えたも御存じない(いものにえたもごぞんじない)
- 御釜を起こす(おかまをおこす)
- お釈迦様でも御存知あるまい(おしゃかさまでもごぞんじあるまい)
- お安い御用(おやすいごよう)
- 御の字(おんのじ)
- 攻撃は最大の防御(こうげきはさいだいのぼうぎょ)
- 御意見五両、堪忍十両(ごいけんごりょう、かんにんじゅうりょう)
- 御機嫌を伺う(ごきげんをうかがう)
「神」を含むことわざ
- 挨拶は時の氏神(あいさつはときのうじがみ)
- 商人の嘘は神もお許し(あきんどのうそはかみもおゆるし)
- 過ちは人の常、許すは神の業(あやまちはひとのつね、ゆるすはかみのわざ)
- 過つは人の性、許すは神の心(あやまつはひとのさが、ゆるすはかみのこころ)
- 祈らずとても神や守らん(いのらずとてもかみやまもらん)
- 臆病の神降ろし(おくびょうのかみおろし)
- 恐れ入谷の鬼子母神(おそれいりやのきしもじん)
- 怪力乱神を語らず(かいりょくらんしんをかたらず)
- 稼ぐに追い抜く貧乏神(かせぐにおいぬくびんぼうがみ)
「酒」を含むことわざ
- 赤いは酒の咎(あかいはさけのとが)
- 朝酒は門田を売っても飲め(あさざけはかどたをうってものめ)
- 新しい酒は新しい革袋に盛れ(あたらしいさけはあたらしいかわぶくろにもれ)
- 新しい酒を古い革袋に盛る(あたらしいさけをふるいかわぶくろにもる)
- 新しき葡萄酒は新しき革袋に入れよ(あたらしきぶどうしゅはあたらしきかわぶくろにいれよ)
- 一杯は人酒を飲む、二杯は酒酒を飲む、三杯は酒人を飲む(いっぱいはひとさけをのむ、にはいはさけさけをのむ、さんばいはさけひとをのむ)
- 後ろに柱前に酒(うしろにはしらまえにさけ)
- お情けより樽の酒(おなさけよりたるのさけ)
- 親の意見と冷や酒は後で利く(おやのいけんとひやざけはあとできく)



