挨拶は時の氏神とは
挨拶は時の氏神
あいさつはときのうじがみ
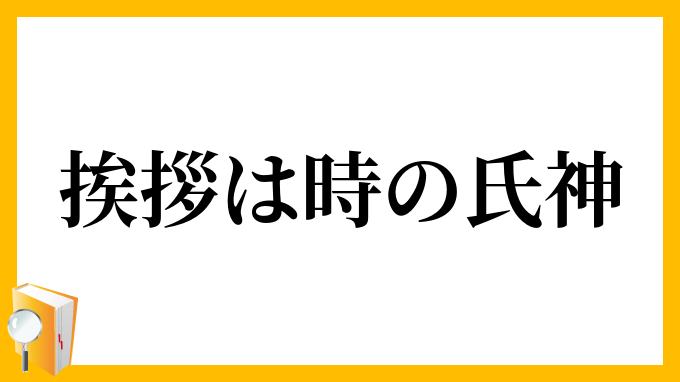
| 言葉 | 挨拶は時の氏神 |
|---|---|
| 読み方 | あいさつはときのうじがみ |
| 意味 | 争いごとの仲裁をしてくれる人は氏神様のようにありがたいものなので、その仲裁に従うのがよいということ。
「挨拶」は仲裁の意味。 「仲裁は時の氏神」ともいう。 |
| 異形 | 仲裁は時の氏神(ちゅうさいはときのうじがみ) |
| 使用語彙 | 挨拶 / 氏神 / 氏 |
| 使用漢字 | 挨 / 拶 / 時 / 氏 / 神 / 仲 / 裁 |
「挨」を含むことわざ
- 挨拶は時の氏神(あいさつはときのうじがみ)
- 挨拶より円札(あいさつよりえんさつ)
「拶」を含むことわざ
- 挨拶は時の氏神(あいさつはときのうじがみ)
- 挨拶より円札(あいさつよりえんさつ)
「時」を含むことわざ
- 朝顔の花一時(あさがおのはなひととき)
- 朝の一時は晩の二時に当たる(あさのひとときはばんのふたときにあたる)
- あの声で蜥蜴食らうか時鳥(あのこえでとかげくらうかほととぎす)
- ある時は米の飯(あるときはこめのめし)
- ある時払いの催促なし(あるときばらいのさいそくなし)
- いざという時(いざというとき)
- 何時にない(いつにない)
- 今を時めく(いまをときめく)
- 飢えたる時は食を択ばず(うえたるときはしょくをえらばず)
「氏」を含むことわざ
- 挨拶は時の氏神(あいさつはときのうじがみ)
- 氏なくして玉の輿(うじなくしてたまのこし)
- 氏より育ち(うじよりそだち)
- 女は氏無うて玉の輿に乗る(おんなはうじのうてたまのこしにのる)
- 和氏の璧(かしのたま)
- 時の氏神(ときのうじがみ)
「神」を含むことわざ
- 商人の嘘は神もお許し(あきんどのうそはかみもおゆるし)
- 過つは人の性、許すは神の心(あやまつはひとのさが、ゆるすはかみのこころ)
- 祈らずとても神や守らん(いのらずとてもかみやまもらん)
- 臆病の神降ろし(おくびょうのかみおろし)
- 恐れ入谷の鬼子母神(おそれいりやのきしもじん)
- 御神酒上がらぬ神はない(おみきあがらぬかみはない)
- 怪力乱神を語らず(かいりょくらんしんをかたらず)
- 稼ぐに追い抜く貧乏神(かせぐにおいぬくびんぼうがみ)
- 叶わぬ時の神頼み(かなわぬときのかみだのみ)
「仲」を含むことわざ
- いい仲になる(いいなかになる)
- 親子の仲でも金銭は他人(おやこのなかでもきんせんはたにん)
- 犬猿の仲(けんえんのなか)
- 死せる孔明、生ける仲達を走らす(しせるこうめい、いけるちゅうたつをはしらす)
- 親しき仲に垣をせよ(したしきなかにかきをせよ)
- 親しき仲にも礼儀あり(したしきなかにもれいぎあり)
- 遠くて近きは男女の仲(とおくてちかきはだんじょのなか)
- 仲立ちより逆立ち(なかだちよりさかだち)
- 仲に立つ(なかにたつ)
「裁」を含むことわざ
- 仲裁は時の氏神(ちゅうさいはときのうじがみ)



