お釈迦様でも気がつくまいとは
お釈迦様でも気がつくまい
おしゃかさまでもきがつくまい
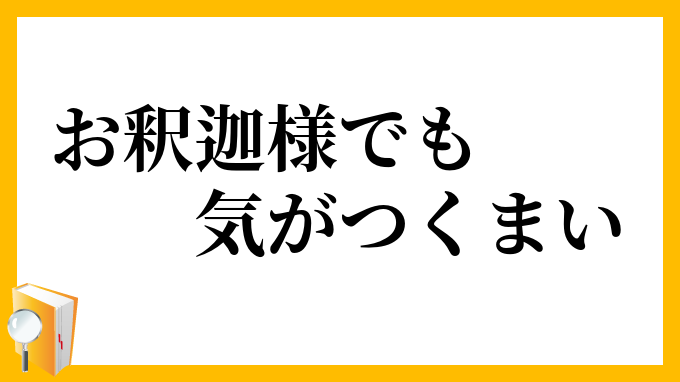
| 言葉 | お釈迦様でも気がつくまい |
|---|---|
| 読み方 | おしゃかさまでもきがつくまい |
| 意味 | 誰も気がつかないだろう、誰も知らないだろうを強調していう言葉。
何でもお見通しのお釈迦様でも知らないだろうとの意から。 「お釈迦様でも御存知あるまい」ともいう。 |
| 異形 | お釈迦様でも御存知あるまい(おしゃかさまでもごぞんじあるまい) |
| 使用語彙 | お釈迦 / 釈迦 / まい |
| 使用漢字 | 釈 / 迦 / 様 / 気 / 御 / 存 / 知 |
「釈」を含むことわざ
- 遠慮会釈なく(えんりょえしゃくなく)
- 遠慮会釈もない(えんりょえしゃくもない)
- お釈迦になる(おしゃかになる)
- 釈迦に宗旨なし(しゃかにしゅうしなし)
- 釈迦に説法(しゃかにせっぽう)
- 釈迦に説法、孔子に悟道(しゃかにせっぽう、こうしにごどう)
- 宗旨の争い釈迦の恥(しゅうしのあらそいしゃかのはじ)
- 世渡りの殺生は釈迦も許す(よわたりのせっしょうはしゃかもゆるす)
「迦」を含むことわざ
- お釈迦になる(おしゃかになる)
- 釈迦に宗旨なし(しゃかにしゅうしなし)
- 釈迦に説法(しゃかにせっぽう)
- 釈迦に説法、孔子に悟道(しゃかにせっぽう、こうしにごどう)
- 宗旨の争い釈迦の恥(しゅうしのあらそいしゃかのはじ)
- 世渡りの殺生は釈迦も許す(よわたりのせっしょうはしゃかもゆるす)
「様」を含むことわざ
- 嘘をつくと閻魔様に舌を抜かれる(うそをつくとえんまさまにしたをぬかれる)
- 売家と唐様で書く三代目(うりいえとからようでかくさんだいめ)
- お医者様でも有馬の湯でも惚れた病は治りゃせぬ(おいしゃさまでもありまのゆでもほれたやまいはなおりゃせぬ)
- お医者様でも草津の湯でも惚れた病は治りゃせぬ(おいしゃさまでもくさつのゆでもほれたやまいはなおりゃせぬ)
- 陰では王様の事も言う(かげではおうさまのこともいう)
- 神様にも祝詞(かみさまにものりと)
- 神様はお見通し(かみさまはおみとおし)
- 米の飯と天道様はどこへ行っても付いて回る(こめのめしとてんとうさまはどこへいってもついてまわる)
「気」を含むことわざ
- 味も素っ気もない(あじもそっけもない)
- 頭から湯気を立てる(あたまからゆげをたてる)
- 頭に湯気を立てる(あたまにゆげをたてる)
- 頭禿げても浮気はやまぬ(あたまはげてもうわきはやまぬ)
- 徒の悋気(あだのりんき)
- 呆気に取られる(あっけにとられる)
- 家鴨も鴨の気位(あひるもかものきぐらい)
- 雨の降る日は天気が悪い(あめのふるひはてんきがわるい)
- いい気なものだ(いいきなものだ)
- いい気になる(いいきになる)
「御」を含むことわざ
- 晏子の御(あんしのぎょ)
- 芋の煮えたも御存じない(いものにえたもごぞんじない)
- 御釜を起こす(おかまをおこす)
- 御神酒上がらぬ神はない(おみきあがらぬかみはない)
- お安い御用(おやすいごよう)
- 御の字(おんのじ)
- 攻撃は最大の防御(こうげきはさいだいのぼうぎょ)
- 御意見五両、堪忍十両(ごいけんごりょう、かんにんじゅうりょう)
- 御機嫌を伺う(ごきげんをうかがう)
「存」を含むことわざ
- 芋の煮えたも御存じない(いものにえたもごぞんじない)
- 運用の妙は一心に存す(うんようのみょうはいっしんにそんす)
- 危急存亡の秋(ききゅうそんぼうのとき)
- 知らぬ存ぜぬ(しらぬぞんぜぬ)
- 存養(そんよう)
- 歯亡びて舌存す(はほろびてしたそんす)



