竿竹で星を打つとは
竿竹で星を打つ
さおだけでほしをうつ
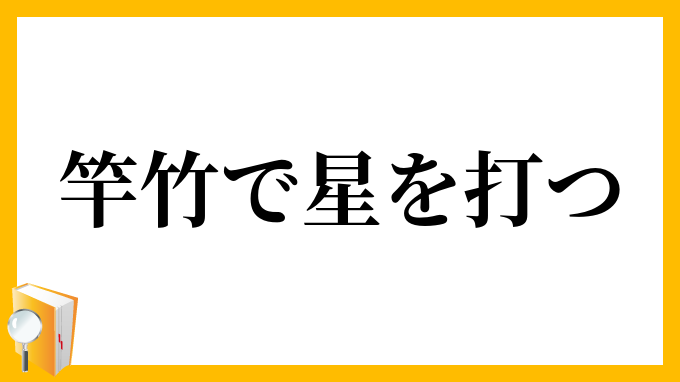
| 言葉 | 竿竹で星を打つ |
|---|---|
| 読み方 | さおだけでほしをうつ |
| 意味 | 不可能なことをしようとする愚かさのたとえ。また、思うところに手が届かないもどかしさのたとえ
竿竹で天にある星を打ち落とすとの意から。 |
| 類句 | 蒟蒻で石垣を築く(こんにゃくでいしがきをきずく) |
| 使用語彙 | 竿竹 / 竿 |
| 使用漢字 | 竿 / 竹 / 星 / 打 |
「竿」を含むことわざ
- 竿竹で星を打つ(さおだけでほしをうつ)
- 竿の先の鈴(さおのさきのすず)
- 百尺竿頭一歩を進む(ひゃくしゃくかんとういっぽをすすむ)
「竹」を含むことわざ
- 木七竹八塀十郎(きしちたけはちへいじゅうろう)
- 木に竹を接ぐ(きにたけをつぐ)
- 木もと竹うら(きもとたけうら)
- 胸中、成竹あり(きょうちゅう、せいちくあり)
- 功名を竹帛に垂る(こうみょうをちくはくにたる)
- 地震の時は竹薮に逃げろ(じしんのときはたけやぶににげろ)
- 成竹(せいちく)
- 竹と人の心の直ぐなのは少ない(たけとひとのこころのすぐなのはすくない)
- 竹に油を塗る(たけにあぶらをぬる)
「星」を含むことわざ
- 甲斐なき星が夜を明かす(かいなきほしがよをあかす)
- 勝ち星を拾う(かちぼしをひろう)
- 巨星墜つ(きょせいおつ)
- 綺羅星の如し(きらぼしのごとし)
- 彗星の如く(すいせいのごとく)
- 図星を指す(ずぼしをさす)
- 名のない星は宵から出る(なのないほしはよいからでる)
- 星が割れる(ほしがわれる)
- 星を挙げる(ほしをあげる)



