持てる者と持たざる者とは
持てる者と持たざる者
もてるものともたざるもの
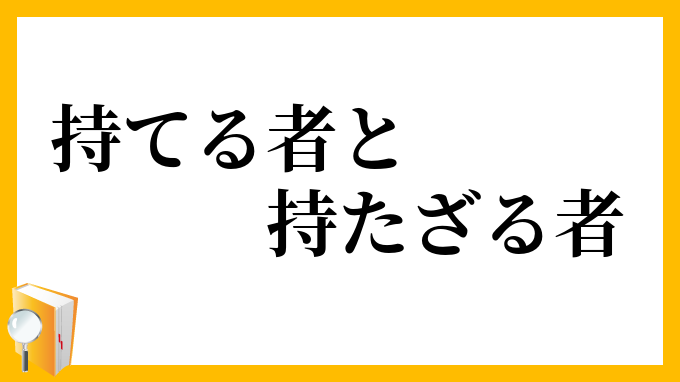
| 言葉 | 持てる者と持たざる者 |
|---|---|
| 読み方 | もてるものともたざるもの |
| 意味 | 世の中は財産を持つ豊かな者と、それを持たない貧しい者の二種類しかないということ。 |
| 場面用途 | 貧乏・貧しい |
| 使用漢字 | 持 / 者 |
「持」を含むことわざ
- 浮世は回り持ち(うきよはまわりもち)
- 馬持たずに馬貸すな(うまもたずにうまかすな)
- 江戸っ子は宵越しの銭は持たぬ(えどっこはよいごしのぜにはもたぬ)
- 縁の下の力持ち(えんのしたのちからもち)
- 大船に乗った気持ち(おおぶねにのったきもち)
- 置き酌失礼、持たぬが不調法(おきじゃくしつれい、もたぬがぶちょうほう)
- お椀を持たぬ乞食はない(おわんをもたぬこじきはない)
- 肩を持つ(かたをもつ)
- 金は天下の回り持ち(かねはてんかのまわりもち)
- 金持ち、金使わず(かねもち、かねつかわず)
「者」を含むことわざ
- 愛出ずる者は愛返り、福往く者は福来る(あいいずるものはあいかえり、ふくゆくものはふくきたる)
- 青表紙を叩いた者にはかなわぬ(あおびょうしをたたいたものにはかなわぬ)
- 赤子のうちは七国七里の者に似る(あかごのうちはななくにななさとのものににる)
- 垢で死んだ者はない(あかでしんだものはない)
- 当たった者のふの悪さ(あたったもののふのわるさ)
- 新たに沐する者は必ず冠を弾く(あらたにもくするものはかならずかんむりをはじく)
- 医者が取るか坊主が取るか(いしゃがとるかぼうずがとるか)
- 医者寒からず儒者寒し(いしゃさむからずじゅしゃさむし)
- 医者上手にかかり下手(いしゃじょうずにかかりべた)
- 医者と味噌は古いほどよい(いしゃとみそはふるいほどよい)



