夜となく昼となくとは
夜となく昼となく
よるとなくひるとなく
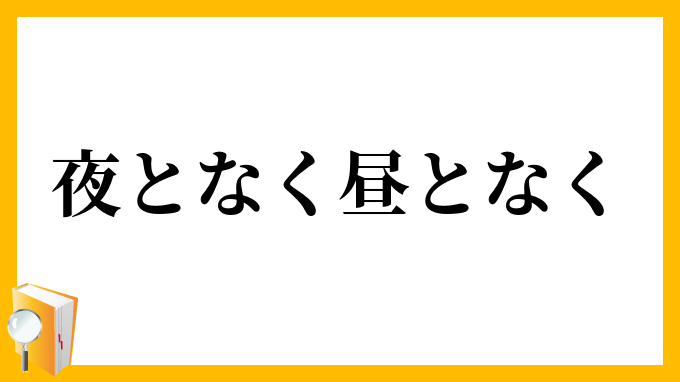
| 言葉 | 夜となく昼となく |
|---|---|
| 読み方 | よるとなくひるとなく |
| 意味 | 夜も昼も関係なく。いつでも。 |
| 類句 | 昼夜を分かたず(ちゅうやをわかたず) |
| 昼夜を舎かず(ちゅうやをおかず) | |
| 夜を日に継ぐ(よをひにつぐ) | |
| 使用語彙 | 夜 |
| 使用漢字 | 夜 / 昼 |
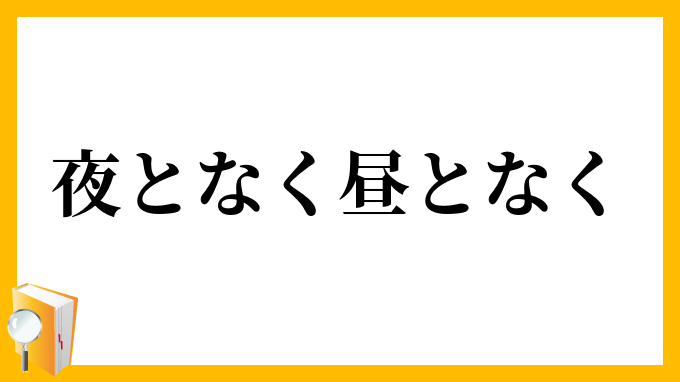
| 言葉 | 夜となく昼となく |
|---|---|
| 読み方 | よるとなくひるとなく |
| 意味 | 夜も昼も関係なく。いつでも。 |
| 類句 | 昼夜を分かたず(ちゅうやをわかたず) |
| 昼夜を舎かず(ちゅうやをおかず) | |
| 夜を日に継ぐ(よをひにつぐ) | |
| 使用語彙 | 夜 |
| 使用漢字 | 夜 / 昼 |