両方立てれば身が立たぬとは
両方立てれば身が立たぬ
りょうほうたてればみがたたぬ
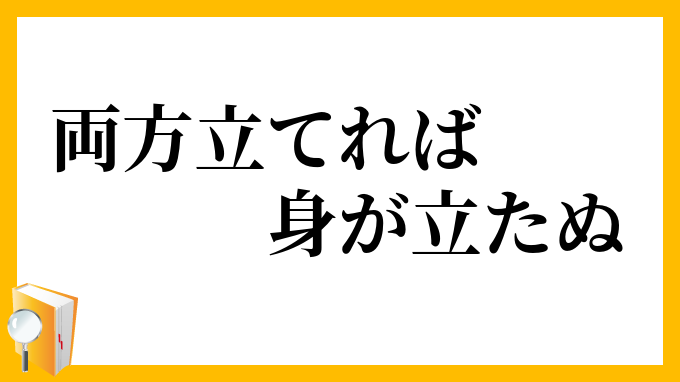
| 言葉 | 両方立てれば身が立たぬ |
|---|---|
| 読み方 | りょうほうたてればみがたたぬ |
| 意味 | 一方に良いようにすれば、他方が不満に思う。どちらにも都合の良いようにするのは難しく、中に入った自分が苦しい立場に立ち、犠牲になってしまうということ。 |
| 類句 | あちら立てればこちらが立たぬ(あちらたてればこちらがたたぬ) |
| 使用語彙 | 身 |
| 使用漢字 | 両 / 方 / 立 / 身 |
「両」を含むことわざ
- 朝起き三両始末五両(あさおきさんりょうしまつごりょう)
- 朝起き千両(あさおきせんりょう)
- 朝起き千両、夜起き百両(あさおきせんりょう、よおきひゃくりょう)
- 後ろ千両前一文(うしろせんりょうまえいちもん)
- 堪忍五両、思案十両(かんにんごりょう、しあんじゅうりょう)
- 堪忍五両、負けて三両(かんにんごりょう、まけてさんりょう)
- がったり三両(がったりさんりょう)
- 車の両輪(くるまのりょうりん)
- 喧嘩両成敗(けんかりょうせいばい)
- 御意見五両、堪忍十両(ごいけんごりょう、かんにんじゅうりょう)
「方」を含むことわざ
- 明後日の方(あさってのほう)
- 彼方立てれば此方が立たぬ(あちらたてればこちらがたたぬ)
- 上を見れば方図がない(うえをみればほうずがない)
- 嘘も方便(うそもほうべん)
- 親方思いの主倒し(おやかたおもいのしゅたおし)
- 親方日の丸(おやかたひのまる)
- 方が付く(かたがつく)
- 方を付ける(かたをつける)
- 滑り道とお経は早い方がよい(すべりみちとおきょうははやいほうがよい)
- 滑り道と観音経は早い方がよい(すべりみちとかんのんきょうははやいほうがよい)
「立」を含むことわざ
- 開いた口に戸は立てられぬ(あいたくちにはとはたてられぬ)
- 愛立てないは祖母育ち(あいだてないはばばそだち)
- 間に立つ(あいだにたつ)
- 青筋を立てる(あおすじをたてる)
- 証が立つ(あかしがたつ)
- 証を立てる(あかしをたてる)
- 秋風が立つ(あきかぜがたつ)
- 商人と屏風は直ぐには立たぬ(あきんどとびょうぶはすぐにはたたぬ)
- 商人と屏風は曲がらねば立たぬ(あきんどとびょうぶはまがらねばたたぬ)
- 足下から鳥が立つ(あしもとからとりがたつ)



