錦の袋に糞を包むとは
錦の袋に糞を包む
にしきのふくろにふんをつつむ
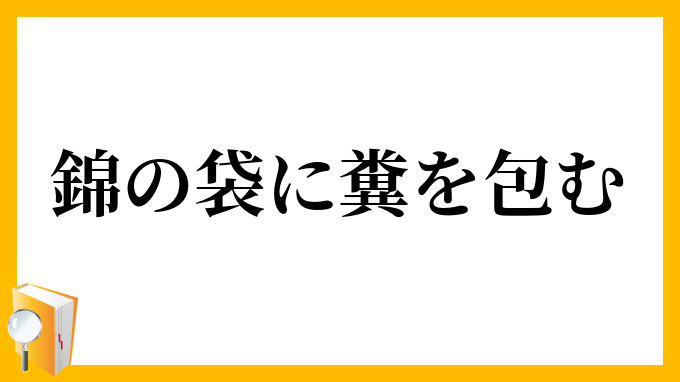
| 言葉 | 錦の袋に糞を包む |
|---|---|
| 読み方 | にしきのふくろにふんをつつむ |
| 意味 | 外観が立派で中身が見劣りすることのたとえ。 |
| 類句 | 重箱に煮染め |
| 使用漢字 | 錦 / 袋 / 糞 / 包 |
「錦」を含むことわざ
- 衣錦の栄(いきんのえい)
- 内裸でも外錦(うちはだかでもそとにしき)
- 親は木綿着る、子は錦着る(おやはもめんきる、こはにしききる)
- 昨日の襤褸、今日の錦(きのうのつづれ、きょうのにしき)
- 昨日の錦、今日の襤褸(きのうのにしき、きょうのつづれ)
- 今日の襤褸、明日の錦(きょうのつづれ、あすのにしき)
- 錦衣を着て故郷に帰る(きんいをきてこきょうにかえる)
- 錦上、花を添える(きんじょう、はなをそえる)
- 故郷へ錦を飾る(こきょうへにしきをかざる)
- 断錦(だんきん)
「袋」を含むことわざ
- 新しい酒は新しい革袋に盛れ(あたらしいさけはあたらしいかわぶくろにもれ)
- 新しい酒を古い革袋に盛る(あたらしいさけをふるいかわぶくろにもる)
- 新しき葡萄酒は新しき革袋に入れよ(あたらしきぶどうしゅはあたらしきかわぶくろにいれよ)
- 堪忍袋の緒が切れる(かんにんぶくろのおがきれる)
- 堪忍袋の緒を切らす(かんにんぶくろのおをきらす)
- 堪忍袋の口を開ける(かんにんぶくろのくちをあける)
- 伊達の素足もないから起こる、あれば天鵞絨の足袋も履く(だてのすあしもないからおこる、あればびろうどのたびもはく)
- 袋の中の鼠(ふくろのなかのねずみ)
- 袋の鼠(ふくろのねずみ)
「糞」を含むことわざ
- 金魚の糞(きんぎょのふん)
- 糞食らえ(くそくらえ)
- 糞も味噌も一緒(くそもみそもいっしょ)
- 糞も味噌も一つ(くそもみそもひとつ)
- 糞を食らえ(くそをくらえ)
- 先勝ちは糞勝ち(さきがちはくそがち)
- 自慢の糞は犬も食わぬ(じまんのくそはいぬもくわぬ)
- 蛸の糞で頭へあがる(たこのくそであたまへあがる)
- 猫が糞を隠したよう(ねこがばばをかくしたよう)
「包」を含むことわざ
- オブラートに包む(おぶらーとにつつむ)
- 志は木の葉に包む(こころざしはこのはにつつむ)
- 錦の袋に糞を包む(にしきのふくろにふんをつつむ)
- 真綿に針を包む(まわたにはりをつつむ)
- 綿に針を包む(わたにはりをつつむ)



