応接に暇あらずとは
応接に暇あらず
おうせつにいとまあらず
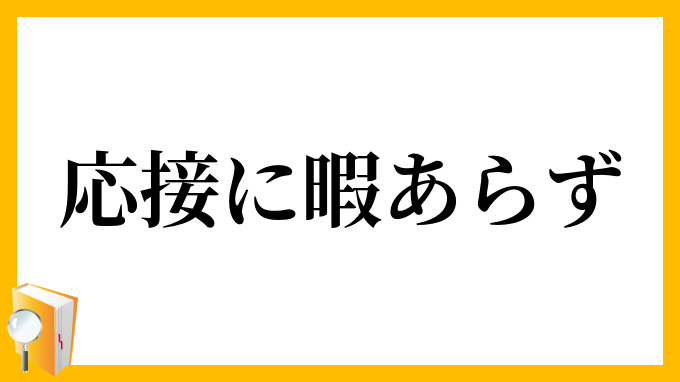
| 言葉 | 応接に暇あらず |
|---|---|
| 読み方 | おうせつにいとまあらず |
| 意味 | 人の相手をするのに追われて休む暇もないようす。また、ものごとが次から次へと起こって多忙なようす。もとは、美しい自然の風景が次から次に展開し、ゆっくり味わう暇がない意から。 |
| 異形 | 応接に暇が無い(おうせつにいとまがない) |
| 使用語彙 | 応接 |
| 使用漢字 | 応 / 接 / 暇 / 無 |
「応」を含むことわざ
「接」を含むことわざ
- 応接に暇あらず(おうせつにいとまあらず)
- 応接に暇が無い(おうせつにいとまがない)
- 木に竹を接ぐ(きにたけをつぐ)
- 踵を接する(きびすをせっする)
- 謦咳に接する(けいがいにせっする)
- 割った茶碗を接いでみる(わったちゃわんをついでみる)
「暇」を含むことわざ
- 寸暇を惜しむ(すんかをおしむ)
- 席暖まるに暇あらず(せきあたたまるにいとまあらず)
- 暇に飽かす(ひまにあかす)
- 暇ほど毒なものはない(ひまほどどくなものはない)
- 暇を出す(ひまをだす)
- 暇を潰す(ひまをつぶす)
- 暇を取る(ひまをとる)
- 暇を盗む(ひまをぬすむ)



