分相応に風が吹くとは
分相応に風が吹く
ぶんそうおうにかぜがふく
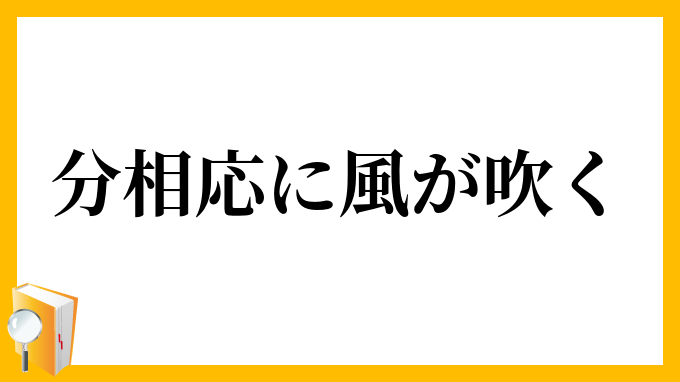
| 言葉 | 分相応に風が吹く |
|---|---|
| 読み方 | ぶんそうおうにかぜがふく |
| 意味 | 人にはそれぞれの身分や地位に応じた生き方があるということ。 |
| 使用語彙 | 分相応 |
| 使用漢字 | 分 / 相 / 応 / 風 / 吹 |
「分」を含むことわざ
- 預かり半分(あずかりはんぶん)
- 預かり半分の主(あずかりはんぶんのぬし)
- 預かり物は半分の主(あずかりものははんぶんのぬし)
- 預かる物は半分の主(あずかるものははんぶんのぬし)
- 一升徳利こけても三分(いっしょうどっくりこけてもさんぶ)
- 一寸の虫にも五分の魂(いっすんのむしにもごぶのたましい)
- 浮世は衣装七分(うきよはいしょうしちぶ)
- 馬の背を分ける(うまのせをわける)
- 鎹分別(かすがいふんべつ)
- 片口聞いて公事を分くるな(かたくちきいてくじをわくるな)
「相」を含むことわざ
- 相性が悪い(あいしょうがわるい)
- 相対のことはこちゃ知らぬ(あいたいのことはこちゃしらぬ)
- 相槌を打つ(あいづちをうつ)
- 相手変われど手前変わらず(あいてかわれどてまえかわらず)
- 相手変われど主変わらず(あいてかわれどぬしかわらず)
- 相手にとって不足はない(あいてにとってふそくはない)
- 相手のさする功名(あいてのさするこうみょう)
- 相手のない喧嘩はできぬ(あいてのないけんかはできぬ)
- 相手見てからの喧嘩声(あいてみてからのけんかごえ)
- 相惚れ自惚れ片惚れ岡惚れ(あいぼれうぬぼれかたぼれおかぼれ)
「応」を含むことわざ
- 一応も二応も(いちおうもにおうも)
- 否が応でも(いやがおうでも)
- 否でも応でも(いやでもおうでも)
- 応接に暇あらず(おうせつにいとまあらず)
- 応接に暇が無い(おうせつにいとまがない)
- 歯応えがある(はごたえがある)
「風」を含むことわざ
- 秋風が立つ(あきかぜがたつ)
- 秋風と夫婦喧嘩は日が入りゃ止む(あきかぜとふうふげんかはひがいりゃやむ)
- 商人と屏風は直ぐには立たぬ(あきんどとびょうぶはすぐにはたたぬ)
- 商人と屏風は曲がらねば立たぬ(あきんどとびょうぶはまがらねばたたぬ)
- 明日は明日の風が吹く(あしたはあしたのかぜがふく)
- あったら口に風邪ひかす(あったらくちにかぜひかす)
- あったら口に風邪をひかす(あったらくちにかぜをひかす)
- 可惜口に風ひかす(あったらくちにかぜをひかす)
- 網の目に風たまらず(あみのめにかぜたまらず)
- 網の目に風たまる(あみのめにかぜたまる)



