一輪咲いても花は花とは
一輪咲いても花は花
いちりんさいてもはなははな
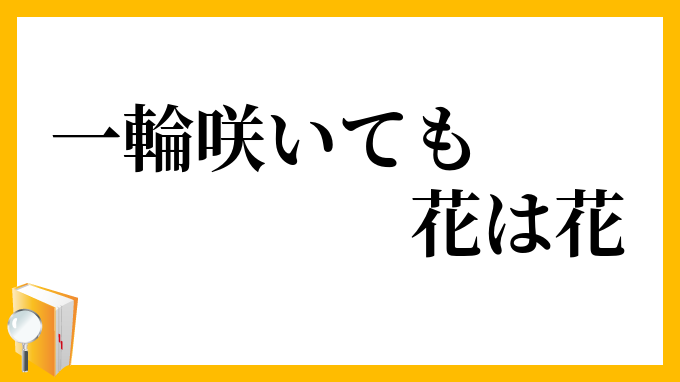
| 言葉 | 一輪咲いても花は花 |
|---|---|
| 読み方 | いちりんさいてもはなははな |
| 意味 | たとえ小さく目立たない存在でも、その存在自身には何ら変わりはないということ。 |
| 類句 | 一合取っても武士は武士(いちごうとってもぶしはぶし) |
| 使用語彙 | 一輪 / 花 |
| 使用漢字 | 一 / 輪 / 咲 / 花 |
「一」を含むことわざ
- 悪は一旦の事なり(あくはいったんのことなり)
- 朝顔の花一時(あさがおのはないっとき)
- 朝の一時は晩の二時に当たる(あさのひとときはばんのふたときにあたる)
- 薊の花も一盛り(あざみのはなもひとさかり)
- あの世の千日、この世の一日(あのよのせんにち、このよのいちにち)
- 危ない橋も一度は渡れ(あぶないはしもいちどはわたれ)
- 粟一粒は汗一粒(あわひとつぶはあせひとつぶ)
- 板子一枚下は地獄(いたごいちまいしたはじごく)
- 一瓜実に二丸顔(いちうりざねににまるがお)
- 一応も二応も(いちおうもにおうも)
「輪」を含むことわざ
- 梅一輪一輪ずつの暖かさ(うめいちりんいちりんずつのあたたかさ)
- 車の両輪(くるまのりょうりん)
- 金輪際(こんりんざい)
- 輪奐(りんかん)
- 輪に輪を掛ける(わにわをかける)
- 輪を掛ける(わをかける)
「咲」を含むことわざ
- 石に花咲く(いしにはなさく)
- 炒り豆に花が咲く(いりまめにはながさく)
- 埋もれ木に花咲く(うもれぎにはなさく)
- 老い木に花咲く(おいきにはなさく)
- 男鰥に蛆が湧き、女寡に花が咲く(おとこやもめにうじがわき、おんなやもめにはながさく)
- 女寡に花が咲く(おんなやもめにはながさく)
- 枯れ木に花咲く(かれきにはなさく)
- 死に花を咲かせる(しにばなをさかせる)
- 死んで花実が咲くものか(しんではなみがさくものか)



