巧言令色、鮮なし仁とは
巧言令色、鮮なし仁
こうげんれいしょく、すくなしじん
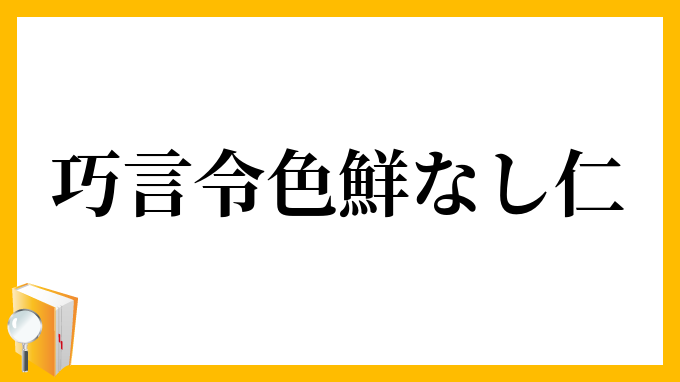
| 言葉 | 巧言令色、鮮なし仁 |
|---|---|
| 読み方 | こうげんれいしょく、すくなしじん |
| 意味 | 口先だけで上手を言い、表情をとりつくろって人に気に入られようとする者には、最高の徳である仁の心が欠けているということ。
「巧言」は巧みな言葉遣い、「令色」は顔色をとりつくろうこと。 「鮮なし」は「少なし」と同じ意味。 |
| 出典 | 『論語』 |
| 使用語彙 | 巧言 / 仁 |
| 使用漢字 | 巧 / 言 / 令 / 色 / 鮮 / 仁 |
「巧」を含むことわざ
- 巧言令色、鮮なし仁(こうげんれいしょく、すくなしじん)
- 巧詐は拙誠に如かず(こうさはせっせいにしかず)
- 巧者貧乏人宝(こうしゃびんぼうひとだから)
- 巧遅は拙速に如かず(こうちはせっそくにしかず)
「言」を含むことわざ
- ああ言えばこう言う(ああいえばこういう)
- 合言葉にする(あいことばにする)
- 呆れて物が言えない(あきれてものがいえない)
- 明日の事を言えば鬼が笑う(あすのことをいえばおにがわらう)
- あっと言う間(あっというま)
- あっと言わせる(あっといわせる)
- 後から剝げる正月言葉(あとからはげるしょうがつことば)
- 穴を掘って言い入れる(あなをほっていいいれる)
- 有り体に言う(ありていにいう)
- 言い得て妙(いいえてみょう)
「令」を含むことわざ
- 巧言令色、鮮なし仁(こうげんれいしょく、すくなしじん)
- 礼は宜しきに随うべし、令は俗に従うべし(れいはよろしきにしたがうべし、れいはぞくにしたがうべし)
「色」を含むことわざ
- 色男、金と力はなかりけり(いろおとこ、かねとちからはなかりけり)
- 色香に迷う(いろかにまよう)
- 色が褪せる(いろがあせる)
- 色気と痔の気のない者はない(いろけとじのけのないものはない)
- 色気より食い気(いろけよりくいけ)
- 色気を示す(いろけをしめす)
- 色気を出す(いろけをだす)
- 色の白いは七難隠す(いろのしろいはしちなんかくす)
- 色は思案の外(いろはしあんのほか)
- 色眼鏡で見る(いろめがねでみる)
「鮮」を含むことわざ
- 巧言令色、鮮なし仁(こうげんれいしょく、すくなしじん)



