勧学院の雀は蒙求を囀るとは
勧学院の雀は蒙求を囀る
かんがくいんのすずめはもうぎゅうをさえずる
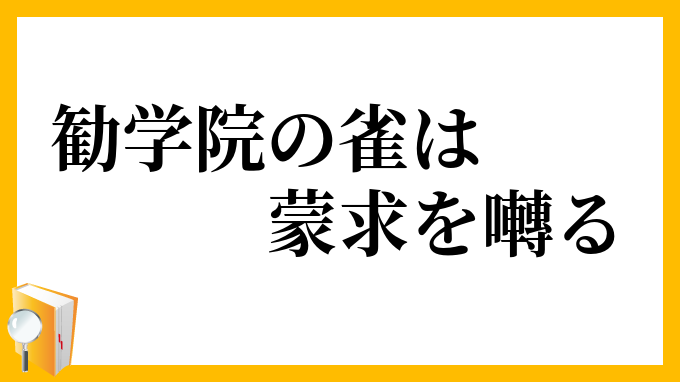
| 言葉 | 勧学院の雀は蒙求を囀る |
|---|---|
| 読み方 | かんがくいんのすずめはもうぎゅうをさえずる |
| 意味 | ふだん見慣れたり聞き慣れたりしていることは、習わなくても自然に身に付くというたとえ。
「勧学院」は、平安時代に藤原氏の子弟を教育した学校。 「蒙求」は、中国唐の時代に書かれた歴史教訓書。 勧学院の雀は、学生が蒙求を読むのを聞き覚えて、それをさえずるようになったということから。 |
| 場面用途 | 無意識・自然に |
| 類句 | 見よう見真似(みようみまね) |
| 門前の小僧、習わぬ経を読む(もんぜんのこぞう、ならわぬきょうをよむ) | |
| 鄭家の奴は詩をうたう(ていかのやっこはしをうたう) | |
| 使用語彙 | 学院 / 雀 / 囀る |
| 使用漢字 | 勧 / 学 / 院 / 雀 / 蒙 / 求 / 囀 |
「勧」を含むことわざ
- 勧学院の雀は蒙求を囀る(かんがくいんのすずめはもうぎゅうをさえずる)
「学」を含むことわざ
- 言う勿れ、今日学ばずして来日ありと(いうなかれ、こんにちまなばずしてらいじつありと)
- 謂う勿れ、今日学ばずして来日ありと(いうなかれ、こんにちまなばずしてらいじつありと)
- 一日一字を学べば三百六十字(いちにちいちじをまなべばさんびゃくろくじゅうじ)
- 一引き、二才、三学問(いちひき、にさい、さんがくもん)
- 田舎の学問より京の昼寝(いなかのがくもんよりきょうのひるね)
- 老いの学問(おいのがくもん)
- 教うるは学ぶの半ば(おしうるはまなぶのなかば)
- 学者の取った天下なし(がくしゃのとったてんかなし)
- 学者むしゃくしゃ(がくしゃむしゃくしゃ)
「院」を含むことわざ
- 勧学院の雀は蒙求を囀る(かんがくいんのすずめはもうぎゅうをさえずる)
「雀」を含むことわざ
- 燕雀安んぞ鴻鵠の志を知らんや(えんじゃくいずくんぞこうこくのこころざしをしらんや)
- 雀、海に入って蛤となる(すずめ、うみにいってはまぐりとなる)
- 雀の千声鶴の一声(すずめのせんこえつるのひとこえ)
- 雀の涙(すずめのなみだ)
- 雀の糠喜び(すずめのぬかよろこび)
- 雀百まで踊り忘れず(すずめひゃくまでおどりわすれず)
- 鷹の前の雀(たかのまえのすずめ)
- 竹に雀(たけにすずめ)
- 闘う雀、人を恐れず(たたかうすずめ、ひとをおそれず)
「蒙」を含むことわざ
- 勧学院の雀は蒙求を囀る(かんがくいんのすずめはもうぎゅうをさえずる)
- 呉下の阿蒙(ごかのあもう)
- 蒙を啓く(もうをひらく)
「求」を含むことわざ
- 陰に託して影を求む(かげにたくしてかげをもとむ)
- 木に縁りて魚を求む(きによりてうおをもとむ)
- 毛を吹いて疵を求む(けをふいてきずをもとむ)
- 七年の病に三年の艾を求む(しちねんのやまいにさんねんのもぐさをもとむ)
- 死中に活を求める(しちゅうにかつをもとめる)
- 死中に生を求める(しちゅうにせいをもとめる)
- 水中に火を求む(すいちゅうにひをもとむ)
- 備わらんことを一人に求むるなかれ(そなわらんことをいちにんにもとむるなかれ)
- 卵を見て時夜を求む(たまごをみてじやをもとむ)
「囀」を含むことわざ
- 勧学院の雀は蒙求を囀る(かんがくいんのすずめはもうぎゅうをさえずる)



