門前の小僧、習わぬ経を読むとは
門前の小僧、習わぬ経を読む
もんぜんのこぞう、ならわぬきょうをよむ
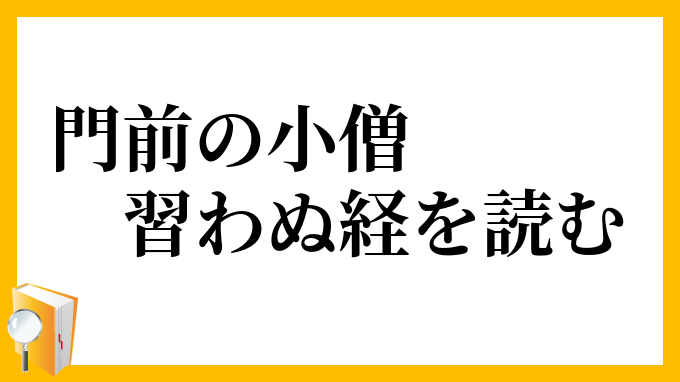
| 言葉 | 門前の小僧、習わぬ経を読む |
|---|---|
| 読み方 | もんぜんのこぞう、ならわぬきょうをよむ |
| 意味 | 普段から見聞きしていると、知らないうちに覚えてしまうことのたとえ。
寺の前に住んでいる子どもたちは、習わなくても自然に経を読めるようになるとの意から。 |
| 場面用途 | 子ども / 無意識・自然に |
| 類句 | 見よう見真似(みようみまね) |
| 鄭家の奴は詩をうたう(ていかのやっこはしをうたう) | |
| 勧学院の雀は蒙求を囀る(かんがくいんのすずめはもうぎゅうをさえずる) | |
| 使用語彙 | 小僧 / 読む |
| 使用漢字 | 門 / 前 / 小 / 僧 / 習 / 経 / 読 |
「門」を含むことわざ
- 商いは門々(あきないはかどかど)
- 商いは門門(あきないはかどかど)
- 朝酒は門田を売っても飲め(あさざけはかどたをうってものめ)
- 倚門の望(いもんのぼう)
- お門が違う(おかどがちがう)
- お門違い(おかどちがい)
- 門松は冥土の旅の一里塚(かどまつはめいどのたびのいちりづか)
- 門松は冥途の旅の一里塚(かどまつはめいどのたびのいちりづか)
- 口は禍の門(くちはわざわいのかど)
- 口は禍の門(くちはわざわいのもん)
「前」を含むことわざ
- 相手変われど手前変わらず(あいてかわれどてまえかわらず)
- 朝飯前(あさめしまえ)
- 朝飯前のお茶漬け(あさめしまえのおちゃづけ)
- 嵐の前の静けさ(あらしのまえのしずけさ)
- 稲荷の前の昼盗人(いなりのまえのひるぬすびと)
- 後ろ千両前一文(うしろせんりょうまえいちもん)
- 後ろに柱前に酒(うしろにはしらまえにさけ)
- 後ろ弁天、前不動(うしろべんてん、まえふどう)
- 家の前の痩せ犬(うちのまえのやせいぬ)
- 馬の前に車をつけるな(うまのまえにくるまをつけるな)
「小」を含むことわざ
- 愛想も小想も尽き果てる(あいそもこそもつきはてる)
- 愛は小出しにせよ(あいはこだしにせよ)
- 戴く物は夏も小袖(いただくものはなつもこそで)
- 因果の小車(いんがのおぐるま)
- 旨い物は小人数(うまいものはこにんずう)
- 大嘘はつくとも小嘘はつくな(おおうそはつくともこうそはつくな)
- 大木の下に小木育たず(おおきのしたにおぎそだたず)
- 大木の下に小木育つ(おおきのしたにおぎそだつ)
- 大遣いより小遣い(おおづかいよりこづかい)
- 大摑みより小摑み(おおづかみよりこづかみ)
「僧」を含むことわざ
- 虚無僧に尺八(こむそうにしゃくはち)
- 似合わぬ僧の腕立て(にあわぬそうのうでたて)
- 門前の小僧、習わぬ経を読む(もんぜんのこぞう、ならわぬきょうをよむ)
「習」を含むことわざ
- 一生添うとは男の習い(いっしょうそうとはおとこのならい)
- 有為転変は世の習い(ういてんぺんはよのならい)
- 移り変わるは浮き世の習い(うつりかわるはうきよのならい)
- 移れば変わる世の習い(うつればかわるよのならい)
- 老いの手習い(おいのてならい)
- 習慣は第二の天性なり(しゅうかんはだいにのてんせいなり)
- 性相近し、習い相遠し(せいあいちかし、ならいあいとおし)
- 習い、性と成る(ならい、せいとなる)
- 習い性となる(ならいせいとなる)
- 習うは一生(ならうはいっしょう)
「経」を含むことわざ
- 経験は愚か者の師(けいけんはおろかもののし)
- 経験は知恵の父記憶の母(けいけんはちえのちちきおくのはは)
- 甲羅を経る(こうらをへる)
- 心ほどの世を経る(こころほどのよをへる)
- 乞食の子も三年経てば三つになる(こじきのこもさんねんたてばみっつになる)
- 三年経てば三つになる(さんねんたてばみっつになる)
- 神経が高ぶる(しんけいがたかぶる)
- 神経が太い(しんけいがふとい)
- 神経に触る(しんけいにさわる)
- 神経を使う(しんけいをつかう)



