湯を沸かして水にするとは
湯を沸かして水にする
ゆをわかしてみずにする
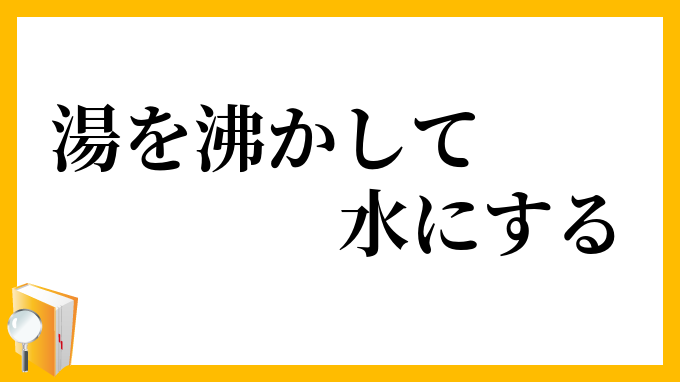
| 言葉 | 湯を沸かして水にする |
|---|---|
| 読み方 | ゆをわかしてみずにする |
| 意味 | せっかくの苦労を無駄にすることのたとえ。
せっかく沸かした湯を使わずに水にしてしまうことから。 「湯を沸かして水に入る」ともいう。 |
| 異形 | 湯を沸かして水に入る(ゆをわかしてみずにいる) |
| 類句 | 骨折り損のくたびれ儲け(ほねおりぞんのくたびれもうけ) |
| 使用語彙 | する / 入る |
| 使用漢字 | 湯 / 沸 / 水 / 入 |
「湯」を含むことわざ
- 頭から湯気を立てる(あたまからゆげをたてる)
- お医者様でも草津の湯でも惚れた病は治りゃせぬ(おいしゃさまでもくさつのゆでもほれたやまいはなおりゃせぬ)
- 白湯を飲むよう(さゆをのむよう)
- 水道の水で産湯を使う(すいどうのみずでうぶゆをつかう)
- 煮え湯を飲まされる(にえゆをのまされる)
- ぬるま湯に浸かる(ぬるまゆにつかる)
- 湯上りにはおじ坊主が惚れる(ゆあがりにはおじぼうずがほれる)
- 湯に入りて湯に入らざれ(ゆにいりてゆにいらざれ)
- 湯の辞儀は水になる(ゆのじぎはみずになる)
- 湯水のように使う(ゆみずのようにつかう)
「沸」を含むことわざ
- 大きい薬缶は沸きが遅い(おおきいやかんはわきがおそい)
- 鼎の沸くが如し(かなえのわくがごとし)
- 血が沸く(ちがわく)
- 鼎沸(ていふつ)
- 臍が茶を沸かす(へそがちゃをわかす)
- 湯を沸かして水にする(ゆをわかしてみずにする)
「水」を含むことわざ
- 明日食う塩辛に今日から水を飲む(あすくうしおからにきょうからみずをのむ)
- 汗水垂らす(あせみずたらす)
- 汗水流す(あせみずながす)
- 頭から水を浴びたよう(あたまからみずをあびたよう)
- 頭から水を掛けられたよう(あたまからみずをかけられたよう)
- 魚心あれば水心(うおごころあればみずごころ)
- 魚と水(うおとみず)
- 魚の水に離れたよう(うおのみずにはなれたよう)
- 魚の水を得たよう(うおのみずをえたよう)
- 魚の目に水見えず(うおのめにみずみえず)



