麻殻に目鼻をつけたようとは
麻殻に目鼻をつけたよう
あさがらにめはなをつけたよう
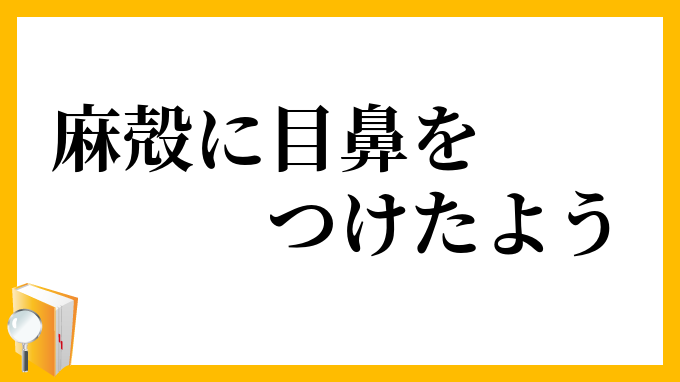
| 言葉 | 麻殻に目鼻をつけたよう |
|---|---|
| 読み方 | あさがらにめはなをつけたよう |
| 意味 | とても痩せた男性の形容。
長くて折れやすい麻殻に目鼻をつけたような男性のことから。 |
| 場面用途 | 目 |
| 使用語彙 | 鼻 |
| 使用漢字 | 麻 / 殻 / 目 / 鼻 |
「麻」を含むことわざ
- 麻殻に目鼻をつけたよう(あさがらにめはなをつけたよう)
- 麻に連るる蓬(あさにつるるよもぎ)
- 麻の中の蓬(あさのなかのよもぎ)
- 快刀、乱麻を断つ(かいとう、らんまをたつ)
- 胡麻を擂る(ごまをする)
- 麻中の蓬(まちゅうのよもぎ)
「殻」を含むことわざ
- 麻殻に目鼻をつけたよう(あさがらにめはなをつけたよう)
- 貝殻で海を量る(かいがらでうみをはかる)
- 殻に籠る(からにこもる)
- 殻に閉じ籠もる(からにとじこもる)
- 餓鬼に苧殻(がきにおがら)
- 蛻の殻(もぬけのから)
「目」を含むことわざ
- 青葉は目の薬(あおばはめのくすり)
- 秋の入り日と年寄りはだんだん落ち目が早くなる(あきのいりひととしよりはだんだんおちめがはやくなる)
- 商人の子は算盤の音で目を覚ます(あきんどのこはそろばんのおとでめをさます)
- 朝題目に夕念仏(あさだいもくにゆうねんぶつ)
- 朝題目に宵念仏(あさだいもくによいねんぶつ)
- 網の目に風たまらず(あみのめにかぜたまらず)
- 網の目に風たまる(あみのめにかぜたまる)
- 網の目を潜る(あみのめをくぐる)
- いい目が出る(いいめがでる)



