火中の栗を拾うとは
火中の栗を拾う
かちゅうのくりをひろう
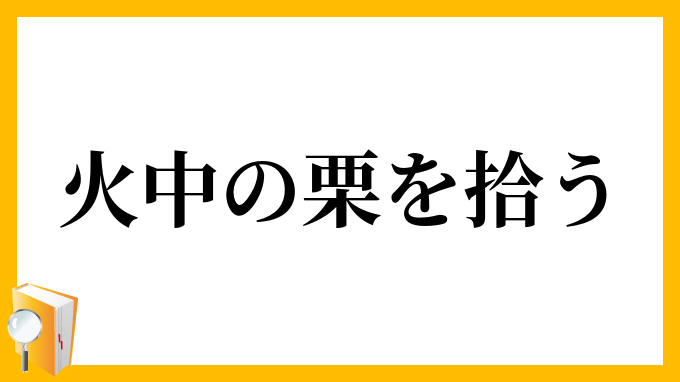
| 言葉 | 火中の栗を拾う |
|---|---|
| 読み方 | かちゅうのくりをひろう |
| 意味 | 自分の利益にはならないにもかかわらず、危険をおかすことのたとえ。猿におだてられた猫が、いろりの中で焼けている栗を拾おうとして大やけどをしたというラ・フォンテーヌ(詩人)の寓話から。 |
| 場面用途 | 危険 / 他人 |
| 使用語彙 | 火中 |
| 使用漢字 | 火 / 中 / 栗 / 拾 |
「火」を含むことわざ
- 秋葉山から火事(あきばさんからかじ)
- 足下に火が付く(あしもとにひがつく)
- 熱火子に払う(あつびこにはらう)
- 油紙に火の付いたよう(あぶらがみにひのついたよう)
- 暗夜に灯火を失う(あんやにともしびをうしなう)
- 家に女房なきは火のない炉のごとし(いえににょうぼうなきはひのないろのごとし)
- 遠水、近火を救わず(えんすい、きんかをすくわず)
- 同い年夫婦は火吹く力もない(おないどしみょうとはひふくちからもない)
- 顔から火が出る(かおからひがでる)
- 火事あとの釘拾い(かじあとのくぎひろい)
「中」を含むことわざ
- 麻の中の蓬(あさのなかのよもぎ)
- 中らずと雖も遠からず(あたらずといえどもとおからず)
- 当て事と越中褌は向こうから外れる(あてごととえっちゅうふんどしはむこうからはずれる)
- 後先息子に中娘(あとさきむすこになかむすめ)
- 石の物言う世の中(いしのものいうよのなか)
- 意中の人(いちゅうのひと)
- 井の中の蛙大海を知らず(いのなかのかわずたいかいをしらず)
- 魚の釜中に遊ぶが如し(うおのふちゅうにあそぶがごとし)
- 海中より盃中に溺死する者多し(かいちゅうよりはいちゅうにできしするものおおし)
- 渦中に巻き込まれる(かちゅうにまきこまれる)
「栗」を含むことわざ
- 毬栗も内から割れる(いがぐりもうちからわれる)
- 火中の栗を拾う(かちゅうのくりをひろう)
- 団栗の背比べ(どんぐりのせいくらべ)
- 桃栗三年柿八年(ももくりさんねんかきはちねん)



