捨てる神あれば拾う神ありとは
捨てる神あれば拾う神あり
すてるかみあればひろうかみあり
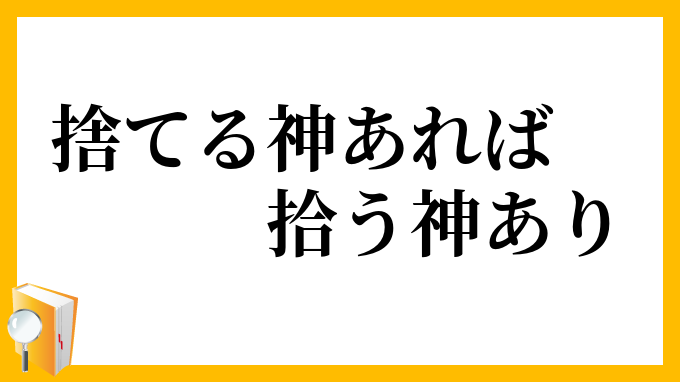
| 言葉 | 捨てる神あれば拾う神あり |
|---|---|
| 読み方 | すてるかみあればひろうかみあり |
| 意味 | 人から見捨てられることもあれば、親切に助けてくれる人もいる。たとえ不運なことがあっても、くよくよするなということ。
「捨てる神あれば助ける神あり」ともいう。 |
| 異形 | 捨てる神あれば助ける神あり(すてるかみあればたすけるかみあり) |
| 使用語彙 | 捨てる / 神 |
| 使用漢字 | 捨 / 神 / 拾 / 助 |
「捨」を含むことわざ
- 聞いた事は聞き捨て(きいたことはききすて)
- 聞き捨てならない(ききずてならない)
- 小異を捨てて大同につく(しょういをすててだいどうにつく)
- 小を捨てて大に就く(しょうをすててだいにつく)
- 捨て石になる(すていしになる)
- 捨て子は世に出る(すてごはよにでる)
- 捨てたものではない(すてたものではない)
- 捨て物は拾い物(すてものはひろいもの)
「神」を含むことわざ
- 挨拶は時の氏神(あいさつはときのうじがみ)
- 商人の嘘は神もお許し(あきんどのうそはかみもおゆるし)
- 過ちは人の常、許すは神の業(あやまちはひとのつね、ゆるすはかみのわざ)
- 過つは人の性、許すは神の心(あやまつはひとのさが、ゆるすはかみのこころ)
- 祈らずとても神や守らん(いのらずとてもかみやまもらん)
- 臆病の神降ろし(おくびょうのかみおろし)
- 恐れ入谷の鬼子母神(おそれいりやのきしもじん)
- 御神酒上がらぬ神はない(おみきあがらぬかみはない)
- 怪力乱神を語らず(かいりょくらんしんをかたらず)
- 稼ぐに追い抜く貧乏神(かせぐにおいぬくびんぼうがみ)
「拾」を含むことわざ
- 落とした物は拾い徳(おとしたものはひろいどく)
- 火事あとの釘拾い(かじあとのくぎひろい)
- 勝ち星を拾う(かちぼしをひろう)
- 火中の栗を拾う(かちゅうのくりをひろう)
- 勝ちを拾う(かちをひろう)
- 木っ端を拾うて材木を流す(こっぱをひろうてざいもくをながす)
- 小爪を拾う(こづめをひろう)
- 白星を拾う(しろぼしをひろう)
- 捨て物は拾い物(すてものはひろいもの)



