禍福は糾える縄の如しとは
禍福は糾える縄の如し
かふくはあざなえるなわのごとし
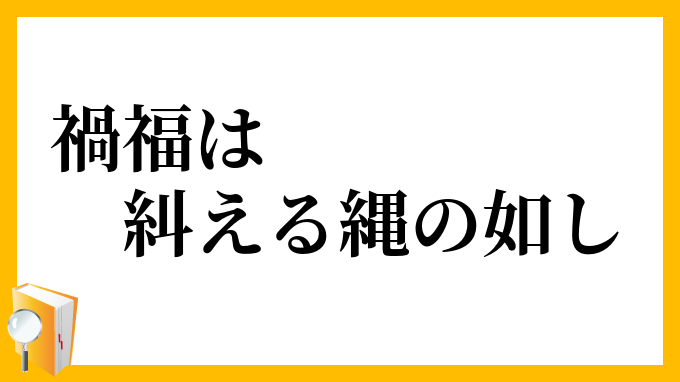
| 言葉 | 禍福は糾える縄の如し |
|---|---|
| 読み方 | かふくはあざなえるなわのごとし |
| 意味 | わざわいと幸福は、より合わせた縄のように表裏一体を成しているということ。「糾う」とは縄をより合わせること。 |
| 出典 | 『史記』 |
| 類句 | 塞翁が馬(さいおうがうま) |
| 沈む瀬あれば浮かぶ瀬あり(しずむせあればうかぶせあり) | |
| 使用語彙 | 禍福 / 縄 / 如し |
| 使用漢字 | 禍 / 福 / 糾 / 縄 / 如 |
「禍」を含むことわざ
- 口は禍の門(くちはわざわいのかど)
- 口は禍の元(くちはわざわいのもと)
- 口は禍の門(くちはわざわいのもん)
- 舌は禍の根(したはわざわいのね)
- 病は口より入り、禍は口より出ず(やまいはくちよりいり、わざわいはくちよりいず)
- 禍は口から(わざわいはくちから)
- 禍も三年経てば用に立つ(わざわいもさんねんたてばようにたつ)
- 禍を転じて福となす(わざわいをてんじてふくとなす)
「福」を含むことわざ
- 愛出ずる者は愛返り、福往く者は福来る(あいいずるものはあいかえり、ふくゆくものはふくきたる)
- 余り茶に福あり(あまりちゃにふくあり)
- 余り物には福がある(あまりものにはふくがある)
- 愚か者に福あり(おろかものにふくあり)
- 残り物には福がある(のこりものにはふくがある)
- 禍を転じて福となす(わざわいをてんじてふくとなす)
- 笑う門には福来る(わらうかどにはふくきたる)
「糾」を含むことわざ
- 禍福は糾える縄の如し(かふくはあざなえるなわのごとし)
「縄」を含むことわざ
- 家売らば縄の値(いえうらばなわのあたい)
- お縄に掛かる(おなわにかかる)
- お縄になる(おなわになる)
- 赤縄を結ぶ(せきじょうをむすぶ)
- 泥棒を捕らえて縄を綯う(どろぼうをとらえてなわをなう)
- 泥棒を見て縄を綯う(どろぼうをみてなわをなう)
- 縄に掛かる(なわにかかる)
- 縄目に掛かる(なわめにかかる)
- 縄目の恥(なわめのはじ)



