無い袖は振れないとは
無い袖は振れない
ないそではふれない
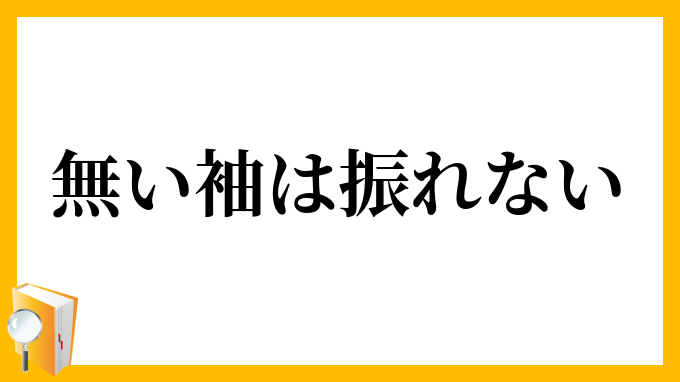
| 言葉 | 無い袖は振れない |
|---|---|
| 読み方 | ないそではふれない |
| 意味 | いくら出したくても持っていなければ出しようがないということ。
着物に袖がなければ、いくら振りたくても振ることはできないとの意から。 |
| 異形 | 無い袖は振れぬ(ないそではふれぬ) |
| 使用漢字 | 無 / 袖 / 振 |
「無」を含むことわざ
- 有っても苦労、無くても苦労(あってもくろう、なくてもくろう)
- 有るか無きか(あるかなきか)
- 有無相通じる(うむあいつうじる)
- 有無を言わせず(うむをいわせず)
- 有無を言わせぬ(うむをいわせぬ)
- 遠慮が無沙汰(えんりょがぶさた)
- 遠慮は無沙汰(えんりょはぶさた)
- 応接に暇が無い(おうせつにいとまがない)
- 奥行きが無い(おくゆきがない)
- 音沙汰が無い(おとざたがない)
「袖」を含むことわざ
- 戴く物は夏も小袖(いただくものはなつもこそで)
- 三十振袖、四十島田(さんじゅうふりそで、しじゅうしまだ)
- 袖から火事(そでからかじ)
- 袖から手を出すも嫌い(そでからてをだすもきらい)
- 袖すり合うも他生の縁(そですりあうもたしょうのえん)
- 袖にする(そでにする)
- 袖の下(そでのした)
- 袖の下に回る子は打たれぬ(そでのしたにまわるこはうたれぬ)
- 袖振り合うも他生の縁(そでふりあうもたしょうのえん)
- 袖触れ合うも他生の縁(そでふれあうもたしょうのえん)



