呆れが礼に来るとは
呆れが礼に来る
あきれがれいにくる
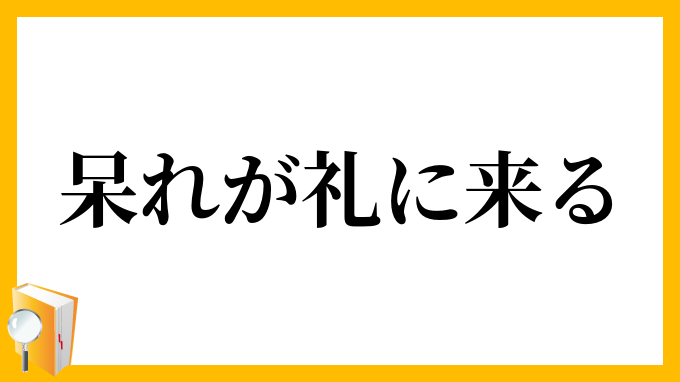
| 言葉 | 呆れが礼に来る |
|---|---|
| 読み方 | あきれがれいにくる |
| 意味 | ひどく呆れることを誇張していうことば。
「呆れがお礼」ともいう。 |
| 異形 | 呆れがお礼(あきれがおれい) |
| 類句 | 開いた口が塞がらない(あいたくちがふさがらない) |
| 呆れて物が言えない(あきれてものがいえない) | |
| 使用漢字 | 呆 / 礼 / 来 |
「呆」を含むことわざ
- 呆れて物が言えない(あきれてものがいえない)
- 呆気に取られる(あっけにとられる)
- 阿呆の三杯汁(あほうのさんばいじる)
- 聞いて呆れる(きいてあきれる)
- 結構は阿呆のうち(けっこうはあほうのうち)
- 正直は阿呆の異名(しょうじきはあほうのいみょう)
- 大根の皮取らぬ阿呆、生姜の皮取る阿呆(だいこんのかわとらぬあほう、しょうがのかわとるあほう)
- 釣りする馬鹿に見る阿呆(つりするばかにみるあほう)
- 冬至十日経てば阿呆でも知る(とうじとおかたてばあほうでもしる)
「礼」を含むことわざ
- 衣食足りて礼節を知る(いしょくたりてれいせつをしる)
- 置き酌失礼、持たぬが不調法(おきじゃくしつれい、もたぬがぶちょうほう)
- 己に克ち、礼に復る(おのれにかち、れいにかえる)
- 神は非礼を受けず(かみはひれいをうけず)
- 三顧の礼(さんこのれい)
- 親しき仲にも礼儀あり(したしきなかにもれいぎあり)
- 知って問うは礼なり(しってとうはれいなり)
- 洗礼を受ける(せんれいをうける)
- 倉廩実ちて礼節を知る(そうりんみちてれいせつをしる)



