昨日は今日の昔とは
昨日は今日の昔
きのうはきょうのむかし
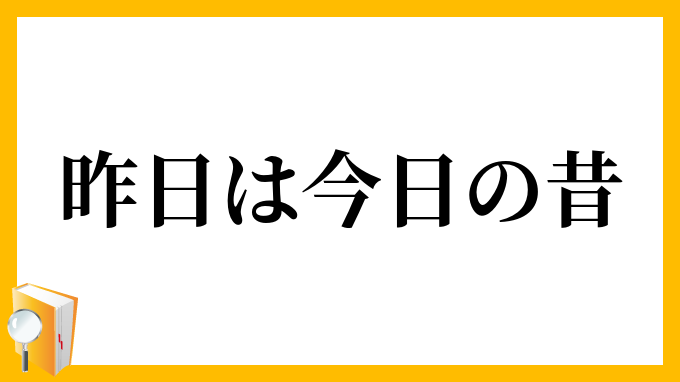
| 言葉 | 昨日は今日の昔 |
|---|---|
| 読み方 | きのうはきょうのむかし |
| 意味 | わずか一日前のことでも、今日から見れば昨日は過去であるということ。 |
| 使用語彙 | 昨日 / 今日 / 昔 |
| 使用漢字 | 昨 / 日 / 今 / 昔 |
「昨」を含むことわざ
- 一昨日来い(おとといこい)
- 昨日の今日(きのうのきょう)
- 昨日の情今日の仇(きのうのじょうきょうのあだ)
- 昨日の襤褸、今日の錦(きのうのつづれ、きょうのにしき)
- 昨日の友は今日の仇(きのうのともはきょうのあだ)
- 昨日の友は今日の敵(きのうのともはきょうのてき)
- 昨日の錦、今日の襤褸(きのうのにしき、きょうのつづれ)
- 昨日の淵は今日の瀬(きのうのふちはきょうのせ)
- 昨日は昨日、今日は今日(きのうはきのう、きょうはきょう)
「日」を含むことわざ
- 秋風と夫婦喧嘩は日が入りゃ止む(あきかぜとふうふげんかはひがいりゃやむ)
- 秋の入り日と年寄りはだんだん落ち目が早くなる(あきのいりひととしよりはだんだんおちめがはやくなる)
- 秋の日と娘の子はくれぬようでくれる(あきのひとむすめのこはくれぬようでくれる)
- 秋の日は釣瓶落とし(あきのひはつるべおとし)
- 秋日和半作(あきびよりはんさく)
- 明後日の方(あさってのほう)
- 朝日が西から出る(あさひがにしからでる)
- 明日は明日の風が吹く(あしたはあしたのかぜがふく)
- 明日ありと思う心の仇桜(あすありとおもうこころのあだざくら)
- 明日食う塩辛に今日から水を飲む(あすくうしおからにきょうからみずをのむ)
「今」を含むことわざ
- 明日食う塩辛に今日から水を飲む(あすくうしおからにきょうからみずをのむ)
- 明日の百より今日の五十(あすのひゃくよりきょうのごじゅう)
- 言う勿れ、今日学ばずして来日ありと(いうなかれ、こんにちまなばずしてらいじつありと)
- 謂う勿れ、今日学ばずして来日ありと(いうなかれ、こんにちまなばずしてらいじつありと)
- 言うまいと思えど今朝の寒さかな(いうまいとおもえどけさのさむさかな)
- 医者の只今(いしゃのただいま)
- 今泣いた烏がもう笑う(いまないたからすがもうわらう)
- 今鳴いた烏がもう笑う(いまないたからすがもうわらう)
- 今の今まで(いまのいままで)
- 今の情けは後の仇(いまのなさけはのちのあだ)



