猿猴が月を取るとは
猿猴が月を取る
えんこうがつきをとる
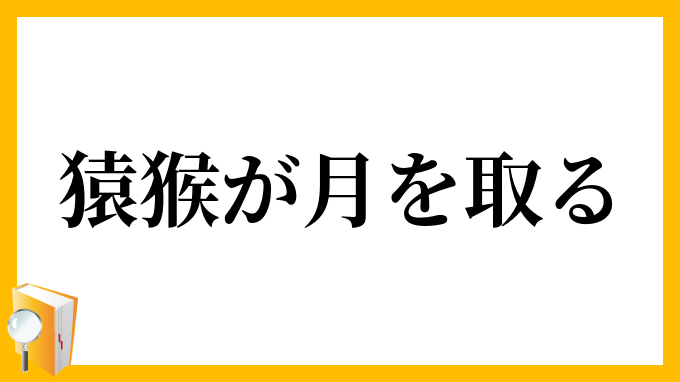
| 言葉 | 猿猴が月を取る |
|---|---|
| 読み方 | えんこうがつきをとる |
| 意味 | 自分の能力をわきまえず、欲張ったまねをして失敗することのたとえ。
猿が水に映った月を取ろうとしたとき、枝が折れ水に落ちて溺れ死んだという故事から。 「猿猴が月」「水の月取る猿」「月の影取る猿」ともいう。 |
| 出典 | 『僧祇律』 |
| 異形 | 猿猴が月(えんこうがつき) |
| 水の月取る猿(みずのつきとるさる) | |
| 月の影取る猿(つきのかげとるましら) | |
| 場面用途 | 才能・能力 |
| 使用語彙 | 猿猴 / 取る |
| 使用漢字 | 猿 / 猴 / 月 / 取 / 水 / 影 |
「猿」を含むことわざ
- 猿臂を伸ばす(えんぴをのばす)
- 木から落ちた猿(きからおちたさる)
- 毛のない猿(けのないさる)
- 犬猿の仲(けんえんのなか)
- 猿知恵(さるぢえ)
- 猿に烏帽子(さるにえぼし)
- 猿に木登り(さるにきのぼり)
- 猿の尻笑い(さるのしりわらい)
- 猿の水練、魚の木登り(さるのすいれん、うおのきのぼり)
「猴」を含むことわざ
- 猿猴が月を取る(えんこうがつきをとる)
- 沐猴にして冠す(もっこうにしてかんす)
「月」を含むことわざ
- 明るけりゃ月夜だと思う(あかるけりゃつきよだとおもう)
- 後から剝げる正月言葉(あとからはげるしょうがつことば)
- 雨夜の月(あまよのつき)
- Rのない月の牡蠣はよくない(あーるのないつきのかきはよくない)
- いつも月夜に米の飯(いつもつきよにこめのめし)
- 英雄、閑日月あり(えいゆう、かんじつげつあり)
- 江戸っ子は五月の鯉の吹き流し(えどっこはさつきのこいのふきながし)
- 親と月夜はいつも良い(おやとつきよはいつもよい)
- 櫂は三年、櫓は三月(かいはさんねん、ろはみつき)
「取」を含むことわざ
- 足掻きが取れない(あがきがとれない)
- 揚げ足を取る(あげあしをとる)
- 足を取られる(あしをとられる)
- 当たりを取る(あたりをとる)
- 呆気に取られる(あっけにとられる)
- 虻蜂取らず(あぶはちとらず)
- 息を引き取る(いきをひきとる)
- 医者が取るか坊主が取るか(いしゃがとるかぼうずがとるか)
- 一合取っても武士は武士(いちごうとってもぶしはぶし)
- 一命を取り止める(いちめいをとりとめる)
「水」を含むことわざ
- 明日食う塩辛に今日から水を飲む(あすくうしおからにきょうからみずをのむ)
- 汗水垂らす(あせみずたらす)
- 汗水流す(あせみずながす)
- 頭から水を浴びたよう(あたまからみずをあびたよう)
- 頭から水を掛けられたよう(あたまからみずをかけられたよう)
- 魚心あれば水心(うおごころあればみずごころ)
- 魚と水(うおとみず)
- 魚の水に離れたよう(うおのみずにはなれたよう)
- 魚の水を得たよう(うおのみずをえたよう)
- 魚の目に水見えず(うおのめにみずみえず)



