六国を滅ぼす者は六国なりとは
六国を滅ぼす者は六国なり
りっこくをほろぼすものはりっこくなり
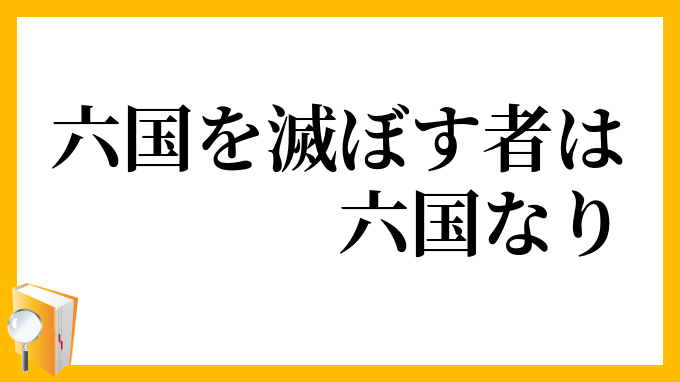
| 言葉 | 六国を滅ぼす者は六国なり |
|---|---|
| 読み方 | りっこくをほろぼすものはりっこくなり |
| 意味 | 国が滅びるのは、国の内部に原因があるということ。また、悪い結果の原因は、自分自身にあることが多いことのたとえ。
「六国」は中国、戦国時代の斉(せい)・楚(そ)・燕(えん)・韓(かん)・魏(ぎ)・趙(ちょう)のこと。 六国が滅びたのは六国相互の争いの結果によるもので、他の国に滅ぼされたわけではないとの意から。 |
| 使用語彙 | 滅ぼす |
| 使用漢字 | 六 / 国 / 滅 / 者 |
「六」を含むことわざ
- 悪妻は六十年の不作(あくさいはろくじゅうねんのふさく)
- 一日一字を学べば三百六十字(いちにちいちじをまなべばさんびゃくろくじゅうじ)
- 一の裏は六(いちのうらはろく)
- 後生願いの六性悪(ごしょうねがいのろくしょうあく)
- 五臓六腑に沁みわたる(ごぞうろっぷにしみわたる)
- 三十六計逃げるに如かず(さんじゅうろっけいにげるにしかず)
- 総領の甚六(そうりょうのじんろく)
- 十日の菊、六日の菖蒲(とおかのきく、むいかのあやめ)
- 女房の悪いは六十年の不作(にょうぼうのわるいはろくじゅうねんのふさく)
- 朋友は六親に叶う(ほうゆうはりくしんにかなう)
「国」を含むことわざ
- 赤子のうちは七国七里の者に似る(あかごのうちはななくにななさとのものににる)
- 家に鼠、国に盗人(いえにねずみ、くににぬすびと)
- 一国一城の主(いっこくいちじょうのあるじ)
- 華胥の国に遊ぶ(かしょのくににあそぶ)
- 国に盗人、家に鼠(くににぬすびと、いえにねずみ)
- 国乱れて忠臣見る(くにみだれてちゅうしんあらわる)
- 国破れて山河在り(くにやぶれてさんがあり)
- 言葉は国の手形(ことばはくにのてがた)
- 三国一(さんごくいち)
- 修身斉家治国平天下(しゅうしんせいかちこくへいてんか)
「滅」を含むことわざ
- 気が滅入る(きがめいる)
- 唇滅びて歯寒し(くちびるほろびてはさむし)
- 生者必滅、会者定離(しょうじゃひつめつ、えしゃじょうり)
- 心頭滅却すれば火もまた涼し(しんとうめっきゃくすればひもまたすずし)
- 心頭を滅却すれば火もまた涼し(しんとうをめっきゃくすればひもまたすずし)
- 大義、親を滅す(たいぎ、しんをめっす)
- 大徳は小怨を滅ぼす(たいとくはしょうえんをほろぼす)
- 大徳は小怨を滅ぼす(だいとくはしょうえんをほろぼす)
- 大徳は小怨を滅す(だいとくはしょうえんをめっす)
- 灯滅せんとして光を増す(とうめっせんとしてひかりをます)
「者」を含むことわざ
- 愛出ずる者は愛返り、福往く者は福来る(あいいずるものはあいかえり、ふくゆくものはふくきたる)
- 青表紙を叩いた者にはかなわぬ(あおびょうしをたたいたものにはかなわぬ)
- 赤子のうちは七国七里の者に似る(あかごのうちはななくにななさとのものににる)
- 垢で死んだ者はない(あかでしんだものはない)
- 当たった者のふの悪さ(あたったもののふのわるさ)
- 新たに沐する者は必ず冠を弾く(あらたにもくするものはかならずかんむりをはじく)
- 医者が取るか坊主が取るか(いしゃがとるかぼうずがとるか)
- 医者寒からず儒者寒し(いしゃさむからずじゅしゃさむし)
- 医者上手にかかり下手(いしゃじょうずにかかりべた)
- 医者と味噌は古いほどよい(いしゃとみそはふるいほどよい)



