短を捨てて長を取るとは
短を捨てて長を取る
たんをすててちょうをとる
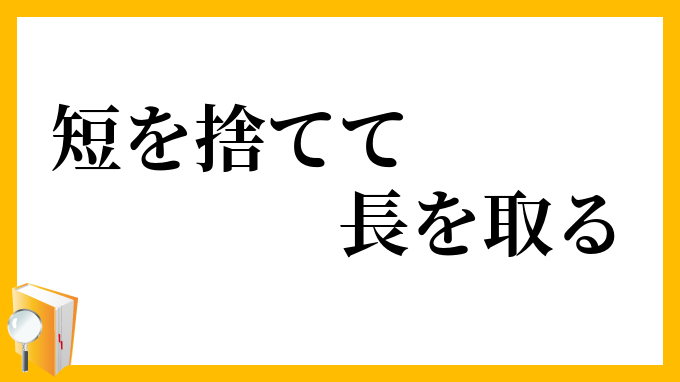
| 言葉 | 短を捨てて長を取る |
|---|---|
| 読み方 | たんをすててちょうをとる |
| 意味 | 欠点や短所を除いて、長所のみを参考として取り入れること。 |
| 出典 | 『漢書』芸文志 |
| 使用語彙 | 取る |
| 使用漢字 | 短 / 捨 / 長 / 取 |
「短」を含むことわざ
- 帯に短し、襷に長し(おびにみじかし、たすきにながし)
- 芥子は気短に搔かせろ(からしはきみじかにかかせろ)
- 気が短い(きがみじかい)
- 芸術は長く、人生は短し(げいじゅつはながく、じんせいはみじかし)
- 尺も短き所あり、寸も長き所あり(しゃくもみじかきところあり、すんもながきところあり)
- 短気は損気(たんきはそんき)
- 短気は未練の初め(たんきはみれんのはじめ)
- 短気は未練の元(たんきはみれんのもと)
- 短気は身を亡ぼす腹切り刀(たんきはみをほろぼすはらきりかたな)
- 短兵急(たんぺいきゅう)
「捨」を含むことわざ
- 聞いた事は聞き捨て(きいたことはききすて)
- 聞き捨てならない(ききずてならない)
- 小異を捨てて大同につく(しょういをすててだいどうにつく)
- 小を捨てて大に就く(しょうをすててだいにつく)
- 捨て石になる(すていしになる)
- 捨て子は世に出る(すてごはよにでる)
- 捨てたものではない(すてたものではない)
- 捨て物は拾い物(すてものはひろいもの)
- 捨てる神あれば助ける神あり(すてるかみあればたすけるかみあり)
- 捨てる神あれば拾う神あり(すてるかみあればひろうかみあり)
「長」を含むことわざ
- 息が長い(いきがながい)
- 行く行くの長居り(いくいくのながおり)
- 一日の長(いちじつのちょう)
- 命長ければ恥多し(いのちながければはじおおし)
- 命長ければ辱多し(いのちながければはじおおし)
- 生まれながらの長老なし(うまれながらのちょうろうなし)
- 江戸の敵を長崎で討つ(えどのかたきをながさきでうつ)
- 帯に短し、襷に長し(おびにみじかし、たすきにながし)
- 風邪は百病の長(かぜはひゃくびょうのおさ)
- 奸知に長ける(かんちにたける)



