貧乏人の子沢山とは
貧乏人の子沢山
びんぼうにんのこだくさん
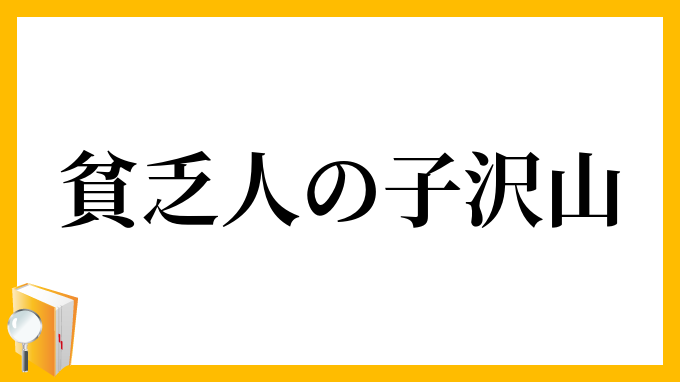
| 言葉 | 貧乏人の子沢山 |
|---|---|
| 読み方 | びんぼうにんのこだくさん |
| 意味 | 貧乏な人にかぎって子どもが多いということ。 |
| 場面用途 | 子ども / 貧乏・貧しい |
| 類句 | 貧乏柿の核沢山(びんぼうがきのさねだくさん) |
| 律義者の子沢山(りちぎもののこだくさん) | |
| 使用語彙 | 子沢山 / 子 |
| 使用漢字 | 貧 / 乏 / 人 / 子 / 沢 / 山 |
「貧」を含むことわざ
- 家貧しくして孝子顕る(いえまずしくしてこうしあらわる)
- 家貧しくして良妻を思う(いえまずしくしてりょうさいをおもう)
- 居ない者貧乏(いないものびんぼう)
- 奢る者は心常に貧し(おごるものはこころつねにまずし)
- 稼ぐに追い付く貧乏無し(かせぐにおいつくびんぼうなし)
- 稼ぐに追い抜く貧乏神(かせぐにおいぬくびんぼうがみ)
- 稼ぐに貧乏追い付かず(かせぐにびんぼうおいつかず)
- 器用貧乏人宝(きようびんぼうひとだから)
- 食わず貧楽高枕(くわずひんらくたかまくら)
- 巧者貧乏人宝(こうしゃびんぼうひとだから)
「乏」を含むことわざ
- 居ない者貧乏(いないものびんぼう)
- 稼ぐに追い付く貧乏無し(かせぐにおいつくびんぼうなし)
- 稼ぐに追い抜く貧乏神(かせぐにおいぬくびんぼうがみ)
- 稼ぐに貧乏追い付かず(かせぐにびんぼうおいつかず)
- 器用貧乏人宝(きようびんぼうひとだから)
- 巧者貧乏人宝(こうしゃびんぼうひとだから)
- 細工貧乏人宝(さいくびんぼうひとだから)
- 酒と朝寝は貧乏の近道(さけとあさねはびんぼうのちかみち)
- 七細工八貧乏(しちざいくはちびんぼう)
- 七細工八貧乏(しちざいくやびんぼう)
「人」を含むことわざ
- 赤の他人(あかのたにん)
- 商人と屏風は直ぐには立たぬ(あきんどとびょうぶはすぐにはたたぬ)
- 商人と屏風は曲がらねば立たぬ(あきんどとびょうぶはまがらねばたたぬ)
- 商人に系図なし(あきんどにけいずなし)
- 商人の嘘は神もお許し(あきんどのうそはかみもおゆるし)
- 商人の子は算盤の音で目を覚ます(あきんどのこはそろばんのおとでめをさます)
- 商人の空値(あきんどのそらね)
- 商人の元値(あきんどのもとね)
- 商人は損していつか倉が建つ(あきんどはそんしていつかくらがたつ)
- 悪人あればこそ善人も顕る(あくにんあればこそぜんにんもあらわる)
「子」を含むことわざ
- 赤子のうちは七国七里の者に似る(あかごのうちはななくにななさとのものににる)
- 赤子の腕を捩じる(あかごのうでをねじる)
- 赤子の手をねじる(あかごのてをねじる)
- 赤子の手を捩じるよう(あかごのてをねじるよう)
- 赤子の手を捻る(あかごのてをひねる)
- 赤子の手を捻るよう(あかごのてをひねるよう)
- 赤子は泣き泣き育つ(あかごはなきなきそだつ)
- 赤子を裸にしたよう(あかごをはだかにしたよう)
- 秋茄子は嫁に食わすな(あきなすはよめにくわすな)
- 秋の日と娘の子はくれぬようでくれる(あきのひとむすめのこはくれぬようでくれる)
「沢」を含むことわざ
- 貧乏柿の核沢山(びんぼうがきのさねだくさん)
- 貧乏人の子沢山(びんぼうにんのこだくさん)
- 律義者の子沢山(りちぎもののこだくさん)



