律義者の子沢山とは
律義者の子沢山
りちぎもののこだくさん
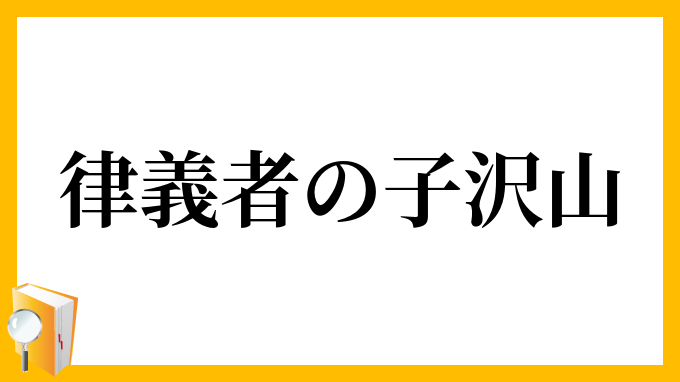
| 言葉 | 律義者の子沢山 |
|---|---|
| 読み方 | りちぎもののこだくさん |
| 意味 | 律義者は、品行方正で家庭円満なので、夫婦仲もよく子どもが多く生まれるということ。 |
| 場面用途 | 夫婦 / 親族 / 出産・誕生 |
| 使用語彙 | 子沢山 / 子 |
| 使用漢字 | 律 / 義 / 者 / 子 / 沢 / 山 |
「律」を含むことわざ
- 必要の前に法律なし(ひつようのまえにほうりつなし)
- 律儀は阿呆の唐名(りちぎはあほうのからな)
- 律義者の子沢山(りちぎもののこだくさん)
- 呂律が回らない(ろれつがまわらない)
「義」を含むことわざ
- 親の恩より義理の恩(おやのおんよりぎりのおん)
- 義理が悪い(ぎりがわるい)
- 義理と褌、欠かされぬ(ぎりとふんどし、かかされぬ)
- 義理にも(ぎりにも)
- 義理張るより頬張れ(ぎりばるよりほおばれ)
- 義理を立てる(ぎりをたてる)
- 義を見てせざるは勇なきなり(ぎをみてせざるはゆうなきなり)
- 仁義を切る(じんぎをきる)
- 大義、親を滅す(たいぎ、しんをめっす)
- 大道廃れて仁義あり(だいどうすたれてじんぎあり)
「者」を含むことわざ
- 愛出ずる者は愛返り、福往く者は福来る(あいいずるものはあいかえり、ふくゆくものはふくきたる)
- 青表紙を叩いた者にはかなわぬ(あおびょうしをたたいたものにはかなわぬ)
- 赤子のうちは七国七里の者に似る(あかごのうちはななくにななさとのものににる)
- 垢で死んだ者はない(あかでしんだものはない)
- 悪女の賢者ぶり(あくじょのけんじゃぶり)
- 当たった者のふの悪さ(あたったもののふのわるさ)
- 新たに沐する者は必ず冠を弾く(あらたにもくするものはかならずかんむりをはじく)
- 医者が取るか坊主が取るか(いしゃがとるかぼうずがとるか)
- 医者寒からず儒者寒し(いしゃさむからずじゅしゃさむし)
- 医者上手にかかり下手(いしゃじょうずにかかりべた)
「子」を含むことわざ
- 赤子のうちは七国七里の者に似る(あかごのうちはななくにななさとのものににる)
- 赤子の腕を捩じる(あかごのうでをねじる)
- 赤子の手を捻る(あかごのてをひねる)
- 赤子は泣き泣き育つ(あかごはなきなきそだつ)
- 赤子を裸にしたよう(あかごをはだかにしたよう)
- 秋茄子は嫁に食わすな(あきなすはよめにくわすな)
- 秋の日と娘の子はくれぬようでくれる(あきのひとむすめのこはくれぬようでくれる)
- 商人の子は算盤の音で目を覚ます(あきんどのこはそろばんのおとでめをさます)
- 熱火子に払う(あつびこにはらう)
- 後先息子に中娘(あとさきむすこになかむすめ)
「沢」を含むことわざ
- 貧乏柿の核沢山(びんぼうがきのさねだくさん)
- 貧乏人の子沢山(びんぼうにんのこだくさん)
- 律義者の子沢山(りちぎもののこだくさん)



