去る者は追わず、来る者は拒まずとは
去る者は追わず、来る者は拒まず
さるものはおわず、きたるものはこばまず
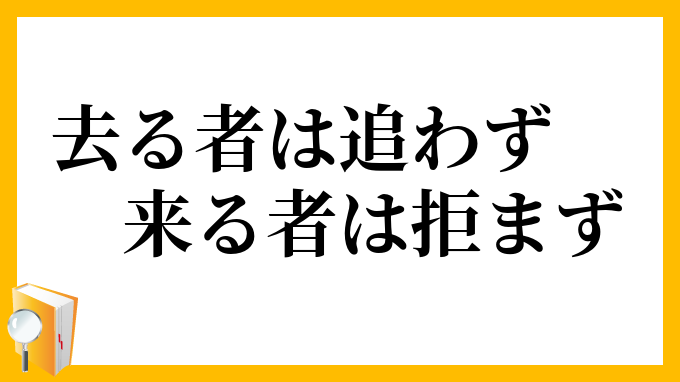
| 言葉 | 去る者は追わず、来る者は拒まず |
|---|---|
| 読み方 | さるものはおわず、きたるものはこばまず |
| 意味 | 自分を信じられずに、離れて行く者を決して引き止めることはしない。自分を信じて頼ってくる者は、どんな人間でも拒まない。その人の心に任せて、決して無理強いはしないということ。 |
| 出典 | 『孟子』 |
| 使用語彙 | 去る / 来る |
| 使用漢字 | 去 / 者 / 追 / 来 / 拒 |
「去」を含むことわざ
- 一難去ってまた一難(いちなんさってまたいちなん)
- 華を去り実に就く(かをさりじつにつく)
- 帰去来(ききょらい)
- 去り跡へ行くとも死に跡へ行くな(さりあとへゆくともしにあとへゆくな)
- 去る者は追わず(さるものはおわず)
- 去る者は日々に疎し(さるものはひびにうとし)
- 去る者は日日に疎し(さるものはひびにうとし)
- 七尺去って師の影を踏まず(しちしゃくさってしのかげをふまず)
- 弟子七尺去って師の影を踏まず(でししちしゃくさってしのかげをふまず)
「者」を含むことわざ
- 愛出ずる者は愛返り、福往く者は福来る(あいいずるものはあいかえり、ふくゆくものはふくきたる)
- 青表紙を叩いた者にはかなわぬ(あおびょうしをたたいたものにはかなわぬ)
- 赤子のうちは七国七里の者に似る(あかごのうちはななくにななさとのものににる)
- 垢で死んだ者はない(あかでしんだものはない)
- 当たった者のふの悪さ(あたったもののふのわるさ)
- 新たに沐する者は必ず冠を弾く(あらたにもくするものはかならずかんむりをはじく)
- 医者が取るか坊主が取るか(いしゃがとるかぼうずがとるか)
- 医者寒からず儒者寒し(いしゃさむからずじゅしゃさむし)
- 医者上手にかかり下手(いしゃじょうずにかかりべた)
- 医者と味噌は古いほどよい(いしゃとみそはふるいほどよい)
「追」を含むことわざ
- 顎で蠅を追う(あごではえをおう)
- 頭の上の蠅も追えない(あたまのうえのはえもおえない)
- 頭の上の蠅も追われぬ(あたまのうえのはえもおわれぬ)
- 頭の上の蠅を追え(あたまのうえのはえをおえ)
- 頭の蠅も追えない(あたまのはえもおえない)
- 跡を追う(あとをおう)
- 追い打ちを掛ける(おいうちをかける)
- 追い討ちを掛ける(おいうちをかける)
- 追い込みを掛ける(おいこみをかける)
- 追いつ追われつ(おいつおわれつ)
「来」を含むことわざ
- 愛出ずる者は愛返り、福往く者は福来る(あいいずるものはあいかえり、ふくゆくものはふくきたる)
- 飽きが来る(あきがくる)
- 呆れが礼に来る(あきれがれいにくる)
- 朝の来ない夜はない(あさのこないよるはない)
- 頭に来る(あたまにくる)
- 言う勿れ、今日学ばずして来日ありと(いうなかれ、こんにちまなばずしてらいじつありと)
- 謂う勿れ、今日学ばずして来日ありと(いうなかれ、こんにちまなばずしてらいじつありと)
- お釣りが来る(おつりがくる)
- 一昨日来い(おとといこい)
- お迎えが来る(おむかえがくる)
「拒」を含むことわざ
- 来る者は拒まず(きたるものはこばまず)
- 来る者は拒まず(くるものはこばまず)
- 去る者は追わず、来る者は拒まず(さるものはおわず、きたるものはこばまず)



